最近頻発している連続殺傷事件についての持論

最近、公共空間で大勢の人を殺傷する凶悪事件が頻発しています。昨年の小田急線刺傷事件、京王線刺傷事件、大阪の心療内科クリニック放火事件、そして先日の東大前刺傷事件等、わずか半年足らずでこんなに発生しているのを見ると、社会がなにか大変な方向に向かっているのではないかという気持ちにならずにはいられません。
ところで、凶悪犯罪が起こると、世間の人々はしばしば次のような意見を主張します。
―加害者は人間らしさの欠如した「異常な」人間である。したがって更正の余地はなく、永久に刑務所に閉じ込めておくか、極刑に処すべきだ。被害者の気持ちを考えてみよ!―
twitterやyahoo!ニュースのコメント欄には、このような意見が至る所に散見され、多くの「いいね!」や賛同するコメントを得ています。
たしかに彼らの犯罪は、なんの罪も落ち度もない人々の命を奪い、人々の心身に取り返しのつかない傷を与え、公共秩序を揺さぶるものであり、決して許されるものではありません。ですから私も彼らを擁護するつもりはありません。彼らはしかるべき裁きを受け、罪を償うべきだと思います。
しかし、一歩立ち止まって考えたい。彼らは世間の人々が言うような、「異常な」人であるというのは本当でしょうか?私にはどうもそうは思えない。私にはこれら一連の犯罪が、頭のイカれた特定の個人が起こした外れ値的現象ではなく、何か社会構造の矛盾や病理の一端を表しているような気がしてなりません。「なぜこのような凶悪犯罪が起こるのか?凶悪犯罪をなくすにはどうしたらいいのか?」ということに、私は関心をもってきました。そして、凶悪犯罪が立て続けに発生した現状を鑑み、これを機に凶悪犯罪についての持論を述べてみたいと思いました。
そこで本稿は、先日2022年1月15日に発生した東大前刺傷事件に焦点を当て、新聞記事を素材にしながら、関係者や識者らの見解を批判的に検討した上で、なぜこのような事件が起きたのか、このような事件が起こらない社会にするにはどうしたらいいのかについて、私の考えを述べます。
また、持論を述べるにあたっては、見田宗介という社会学者の『まなざしの地獄 尽きなく生きることの社会学』という本の議論を参照します。
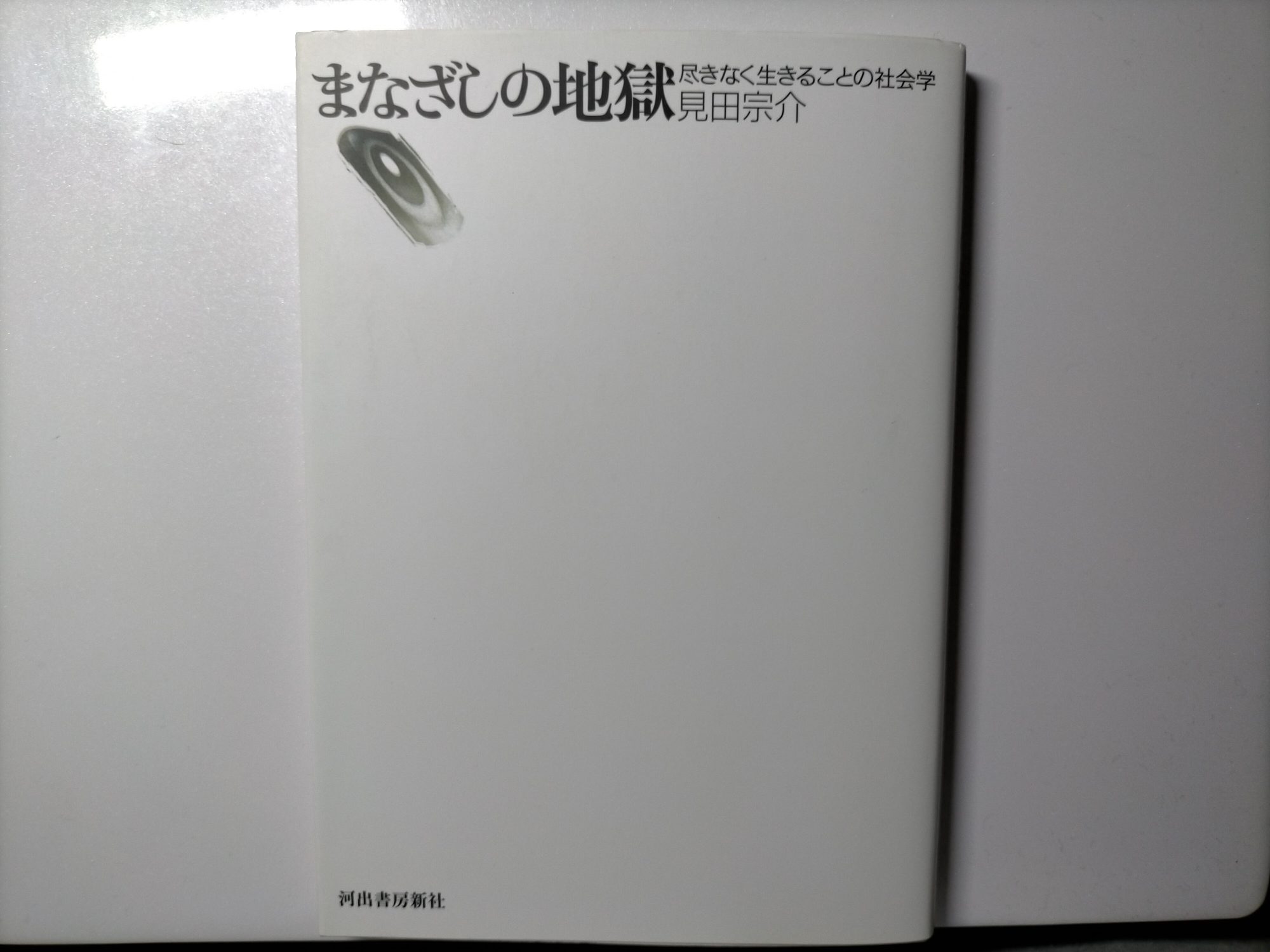
この本は、1960年代に連続射殺事件を起こした永山則夫という死刑囚の半生に着目し、社会の「まなざし」が人間を巧妙に差別し追い詰める構造を明らかにした有名な論考です。この論考が発表されたのは1973年ですが、社会構造が人間の実存に与える意味を克明に描くことに成功した点で、今読んでも示唆に富む研究だと思います。私は本書で行われた分析が、現在多発している凶悪犯罪の分析にも適用しうるのではないかと考え、この本をもとに東大前刺傷事件の検討を行うことにしました。
なお、(※数字)は脚注です。
1.新聞記事の内容
本稿では2022年1月22日付の某地方新聞の記事を素材とします。見出しには「憎しみの象徴 東大に矛先?」とあります。
著作権の都合で記事自体は掲載できませんが、内容は、事件発生から一週間が経過したことを鑑み、識者、学校関係者、社会心理学教授といった専門家を登場させ、それぞれのコメントを踏まえて少年が事件を起こした動機を推測するものになっています。
識者は「勉強に挫折し、こだわり続けてきた東大が憎しみの象徴に変化して矛先が向いたのだろう」と指摘しています。
学校関係者は「新型コロナウイルス禍で行事の多くが中止になり、自分しか見えない状況で孤立感を深め、事件が引き起こされたのではないか」と推察し「他の同級生と比べ、焦りから自分を追い込んでしまったのだろう。変化に気付いてあげられなかった」と悔やんでいます。
新潟青陵大大学院の社会心理学の教授は「少年は自信のあった勉強で挫折し、大きなことをやって世の中に力を示そうと思ったのだろう」と指摘し、「思春期の子どもは悩みがあってもなかなか話さないが、大人は一声掛けるだけでなく、違う環境に連れ出すなどもう一押しすることで本音を聞き出し、心のケアが出来るのではないか」と話しています。
また記事では、少年の話した「医者になれないなら人を殺して罪悪感を背負って切腹しようと考えた」との動機の説明には飛躍が見られるため、今後精神鑑定が行われる可能性についても指摘しています。
2.私の意見
本節では、専門家らの見解を批判的に検討した上で、本事件に対する私なりの見解を表明します。その際、見田宗介の『まなざしの地獄』を適宜引用しながら論を進めていきます。
率直にいって、識者や学校関係者による推測の内容に、納得できなさ―というか反発―を感じる記事でした。
まず、識者の説明からは、少年にとっての「社会」の存在が全く抜け落ちており、全てを少年の心の問題として完結させてしまっています。こういう問題のとらえ方では、社会と少年の間にどのような相互作用があったのかを検討する視点が失われてしまいます。
私が思うに、この犯罪を通して見えてくるのは、少年の「自分自身になろうとする」欲望と、社会の「まなざし」の問題です。
少年にとって、東大に入ることは「自分自身になること」の一環だったと考えられます。東大に入り、やがて医者になり社会で認められることが、少年にとって「自分自身になること」だったわけです。社会(学校の先生、同級生、親といった身近な人物や、受験制度や受験に関するマスメディアの言説等の受験に関わる全てのシステムの総体)もまた、少年に対して「頭のいい子」「優秀な子」というまなざしを向けることで、少年の勉強を促進する機能を果たしていたでしょう。
しかし、一見好ましい相互作用を起こしている少年と社会の欲望には、実はあるズレがあります。少年にとって東大に入ることは「自分自身になること」の一環だと先に述べましたが、社会は少年が「自分自身になること」を求めているのではない。社会がまなざしで欲望していることは、少年が「頭のいい子」「優秀な子」、やがては「東大生」や「医者」という断片的な「記号」として振る舞うことなのです。少年は自己の拡張を欲望しているのに対し、社会は少年の断片化、記号化を欲望しているのです。 このような事態を見田は『まなざしの地獄』でこう述べています。
―「金の卵」としての彼ら(引用者注:1960年代当時に集団就職で上京してきた若者達のこと)を、人手不足の雇用者たちは、優遇し、ちやほやし、「はれものにさわるみたいに」大切にするだろう。だがあくまでもそれは彼が、「やる気をもった家畜」として忍耐強く働く<若年労働力>たる限りにおいてである。ところがN・N(引用者注:永山則夫のこと)にとって(そして多くの「流入青少年」にとって)、上京とは自己解放への企図であった。少なくとも上京に託した夢とは、自己解放の夢である。―
見田宗介(2008)『まなざしの地獄 尽きなく生きることの社会学』河出書房新社 p21~p22
ここに悲劇があります。少年は社会のまなざしに応えて、自己実現のために勉強を頑張れば頑張るほど、社会が少年を記号化するまなざしに絡め取られてしまうのです。しかし、言うまでもなく人間は記号に還元し尽くされる存在ではないから、少年全体からは「優秀な子」「頭のいい子」といった記号に収まりきらない「あまりの部分」がこぼれ落ちてくる。実はその「あまりの部分」こそ、少年の「人格」に他ならないのですが、社会にとって少年の人格は「余計なもの」として切り捨てられてしまうのです。(※1)
再び『まなざしの地獄』から。
―「金の卵」としての彼らの階級的対他存在にとって、このような存在ののりこえへの意思、生の無限性への意欲は、たんに当惑させるものであり、不条理な攪乱要因にすぎない。雇用者たちにしてみれば、このような少年たちの「尽きなく存在し」ようとする欲望くらい、不本意で腹立たしいものはない。・・・もちろん少年のがわからみれば、このような「金の卵」としての自己の階級的対他存在こそはまさしく、一個の自由としての飛翔をとりもちのようにからめとり限界づける他者たちのまなざしの罠に他ならない。―
見田宗介(2008)『まなざしの地獄 尽きなく生きることの社会学』河出書房新社 p22
こうして、少年は勉強を通して自分自身になろうとすればするほど、かえって自己疎外に陥ってしまうという逆説的結果が生じてしまいます。
社会のまなざしに応えようとすれば、「自分自身になること」を諦めなければならない。かといって、自分自身であろうと欲すれば、社会から認められない。この矛盾が臨界点に達したとき、少年は犯行に至ったのです。したがって少年の試みは、社会に反抗することで社会からのまなざしを超克し、自らの人間性を回復しようとするものだった。と私は考えます。
記事によると、少年は「来年、東大を受験する」と、学校名や偏差値(!)とともに叫んだそうです。この事実は、少年にとってこの犯罪が自己の存在証明であったことを如実に表しています。犯罪によって自分を記号化する社会のまなざしを超克し、他の誰でもない「この僕」がここにいるということを示そうとしたのだと思います。
1997年に神戸連続児童殺傷事件を起こした酒鬼薔薇聖斗は、自分を「透明な存在」だと評しました。また、2008年に秋葉原通り魔事件を起こした加藤智大は、ネットの掲示板に書き込んだ自分語りに反応がなかったことを引き金に、犯行に及びました。この点について社会学者の大澤真幸は、二人とも、「(他の誰でもない)自分がここにいる」ことを社会に示そうとして犯行に及んだのだといった見解を『まなざしの地獄』の解説で述べています。私は、今回の少年も彼らの系譜に連なる1人だと思います。
こう書くと、「人間らしさを取り戻すといったって、他にいくらでもやりようはあったはずだ」という反論が予想されます。しかし、そう簡単に言い切れることではないと思います。社会的に「健全な」手段では、結局は社会のまなざしが含む規範を受け入れていることになり、まなざしを超克することにはならないからです。したがって少年にとっては、社会の規範を破ることでしか人間性の回復はなしえないことになる。ここに少年の試みが「犯罪」という形をとらなければならなかった必然性があるのです。
学校関係者は「コロナ禍で孤立感を深めた」「他の同級生と比べて焦りを感じた」のではないかと推測しています。しかし、これらの推測はともに間違っていると私は思います。なぜなら、社会のまなざしを超克し、自らの人間性を回復しようとして行われる犯罪は、古くは1960年代の永山則夫事件から先述の2008年秋葉原通り魔事件に至るまで、コロナ禍になる前からくり返し起こってきたからです。(※2)コロナが問題を悪化させた因子のひとつではありうるとしても、問題の本質はコロナにはありません。また、少年が格闘していたのは、他の同級生達ではなく、その背後に控えている「社会」そのものです。他の同級生と比較して焦りを感じたという見方は、問題を矮小化してしまいます。
新潟青陵大大学院の社会心理学の教授は「少年は自信のあった勉強で挫折し、大きなことをやって世の中に力を示そうと思ったのだろう」と推測していますが、私からすればこれも正しくない。少年が犯罪という大きなことをやったのは、力を示すためではありません。少年が「犯罪」という行為を選んだのは、論理的帰結なのです。社会のまなざしを超克する手段とはすなわち社会規範を侵犯する行為、つまり犯罪に他ならないという論理的帰結です。「大きいことをやってやろう」と意識した「から」大きいことを選択したのではなく、選択された行為が結果として大きいものだったのです。
また同教授は「大人は一声掛けるだけでなく、違う環境に連れ出すなどすることで子どもの本音を聞き出し、心のケアができるのではないか」とも述べています。しかし、この見解はハッキリ言って、子どもをナメていると思います。子どもは憂鬱な気分なんかに悩んでいるのではなく、「社会へ適応すること」と「自分自身になること」の根本的矛盾に悩んでいるのです。それを上手く言語化することができないから、「つらい」「しんどい」「死にたい」という感情の問題として表出しているだけです。問題の本質は「心」ではなく「実存」にあるのです。彼らはその矛盾が容易に解決し得ないことを無意識に察知しているからこそ、犯罪行為で社会を超克しようとするのです。これは一時の気晴らしで解決するような生やさしい問題ではない。もし、この矛盾を解決する「違う環境」なるものがあるとすれば、それは受験や学校そのものからのドロップアウトしかないでしょう。実際、文科省の2021年度『問題行動等調査』によれば、小中学生の不登校は増加傾向にあります(高校生は減少傾向)。このことは不気味な徴候ではないでしょうか・・・。
また記事では、「少年の話した「医者になれないなら人を殺して罪悪感を背負って切腹しようと考えた」との動機の説明には飛躍が見られる」とあります。しかし私が思うに、少年にとっては飛躍などしていない。なぜなら、少年にとって医者になれないことは自己喪失であり、自分自身を取り戻すには、凶悪犯罪を起こして社会のまなざしを超克するという手段しか残されていなかったからです。私達がこれを飛躍だと感じるのは、「例え医者になれなくても人生の選択肢は他にもある」と考えるからですが、この考え方は少年の「自分自身になろうとする」欲求を見落としています。少年にとっては、東大→医者というコースが唯一の「自分自身になる」道であり、それ以外の選択肢は全て自己喪失でしかないのです。そして、そのように少年が思い詰めるに至った背景には、社会が少年を「優秀な子」「未来の東大生や医者」といった断片的な記号として捉えようとするまなざしを、少年が内面化していく過程があったのです。私はそのように考えます。
3.まとめ
本稿では、新聞記事に寄せられた専門家の見解を批判的に検討し、犯罪を少年の心の問題として捉える視点は、少年と社会の相互作用を見落としてしまい、問題の本質を隠蔽してしまうことを指摘しました。それを踏まえて、少年が「自分自身になろうとする」欲望が、少年を記号化する社会のまなざしに絡め取られ、逆説的に自己疎外へと陥り、失われた自分自身を取り戻そうとする結果凶悪犯罪に至るメカニズムを呈示しました。
では、本稿の試みから見えてくることは何か。それは、少年は人間らしさの欠落した「異常な」人間などではなく、むしろ人一倍、自らの人間らしさを必死に取り戻そうとした人間だったということだと思います。端的に言えば、彼は人一倍人間らしい「ゆえに」人一倍非人間的な犯罪に至ったという逆説的な事態が生じたのです。
ここで急いで付け加えると、私は少年を擁護しているのではありません。たまたま居合わせた受験生や通行人という標的は、犯罪の目的からみて全く的外れです。少年は自分と全く関係のない、罪も落ち度もない人々の心身に取り返しのつかない傷を与え、彼らの人生を狂わせました。彼の犯罪はいかなる理由があったとしても許されるものではありません。私が言いたいのは、この犯罪は少年の「異常な」心が引き起こしたのではなく、社会のまなざしという不可視の力が巧妙に少年と相互作用した結果引き起こされたということです。
本節の冒頭で私は、「犯罪を少年の心の問題として捉える視点は、少年と社会の相互作用を見落としてしまい、問題の本質を隠蔽してしまう」と述べました。この点について、私達がくれぐれも忘れてはならないことが一つあります。それは、「私達も犯罪の本質を隠蔽する世論の当事者になりうる」ということです。これを読んでくださっているあなたも、私も、犯罪が少年の「異常な」心が引き起こしたと捉える視点に立った瞬間、問題の本質を隠蔽する世論に加担していることになります。そして、その世論―世間の無理解―こそが、将来同じような凶悪犯罪を生み出す温床になってしまいます。このことはいくら強調してもしきれないと思う。
世論を形成するひとりである限り、あなたも私も当事者です。今回の事件を知って、世の中の善良な心を持つ多くの人々(あなたもその一人のはずです)は、被害者に深く同情し、加害者に強い怒りを感じているかと思います。そして、このような事件が二度と起きない社会にするべきだと心から願っているでしょう。そうであるからこそ、人々は、いや私達は、少年を追い詰めた社会のまなざしのメカニズムに目を向けるべきです。社会構造の非人間的側面に想像力をはたらかせることが、凶悪犯罪を助長する風土を見直すことに繋がり、長い目で見れば社会から凶悪犯罪が消えていくことにつながるのだと、私は考えます。
くどいようですが念押しすると、私は「少年は悪くない!全部社会が悪いのだ!」と言っているのではありません。悪いのは、少年です。私が言いたいのは、「加害者だけを糾弾し、犯罪の厳罰化を声高に叫ぶだけでは、いつまでたっても社会から凶悪犯罪がなくなることはありませんよ」ということです。
本稿では、先般起きた東大前刺傷事件に限定して論を進めてきました。したがって先の結論―少年は人一倍人間的であるゆえに非人間的な犯罪に至った―は、あくまでも本事件に限定された結論です。しかし個人的には、先の結論は今まで起きてきた他の凶悪事件にも、おそらく大なり小なり当てはまることではないか、という直感を抱いています。個々の事例ごとに検証してみないと分からないことではありますが。
4.本論を終えるにあたって
繰り返し述べてきたように、私の考察は、見田宗介という社会学者の『まなざしの地獄―尽きなく生きることの社会学』という本に大きく依拠しています。この本は1960年代に連続射殺事件を起こした永山則夫という死刑囚の半生に焦点を当て、「社会のまなざし」が彼の実存形式を巧妙に規定したメカニズムを明らかにし、凶悪犯罪者を必然的に生み出す社会の構造を暴き出したものです。(※3)
今回私が示した見解は、見田の視点を、私なりに稚拙ながらも直近の事件に適用しようとする試みだと位置づけられます。
また、今回題材とした東大前刺傷事件は、本稿執筆時において捜査が進められている途上にあるため、事件に関する情報及び私の見解は2022年1月25日現在のものです。
5.余談―凶悪犯罪の解明にはどのような心理学や社会学が有効なのか?
以下は余談として、凶悪犯罪のメカニズムの解明や発生の防止という観点からみたとき、人間を研究対象とする学問である心理学や社会学はどのような営みであるべきかについて、私が思うことを述べてみます。東大前刺傷事件と直接に関係する話ではないため(私の中では繋がっていますが)、興味のない方は飛ばしていただいて結構です。ですが、心理学や社会学に関心のある方は読んでいただけたら嬉しいです。
本稿では一貫して、犯罪の原因を少年の「心理」に還元する視点を批判してきました。いってみれば、事件の検討を通して心理学批判をしてきたわけです。とはいえ、凶悪犯罪は滅多におきない現象なわけだから、少年の心理を抜きにして社会的要因だけでメカニズムを説明しようとする手法も限界があります。だから社会学が万能だというわけにもいかない。
では、凶悪犯罪成立のメカニズムを心理学や社会学において捉えるには、どのような認識の枠組み(準拠枠やパラダイムといってもいいかもしれません)が有効なのでしょうか?
思うに、心理学と社会学の根本的問題は、「心」と「社会」を別々のものとして考えている点にあります。まず心的現象が起こる場としての個人がいて、それら個人が集まって社会を形成している。あるいは逆に、まず個人から独立した社会があって、その影響のもとに個人の心的現象が生起している。そのように考えるから、心と社会はどちらが先か、個人差と環境のどちらが重要なのかといった、タマゴが先かニワトリが先かみたいな解決不能な問いに陥ってしまうのではないでしょうか。
そうであるならば、「心」と「社会」は同時に存在する、言い換えれば「この私」という意識とその外部にある「世界」は同時に存在する、つまり「私」すなわち「世界」である、と考えたらどうか?
ここで参考になるのは、哲学者マルティン・ハイデガーの議論です。
彼は、「私」と「世界」は同時に存在し、互いに切り離せない事態であると主張しました。そしてこのような事態を、人間は「世界ー内ー存在(In-der-Welt-sein)」であるという言い方で表しています。
人間は「世界ー内ー存在」であるとはどういう意味か。例えば、演劇を思い浮かべるとわかりやすい(古東,2002)。俳優が舞台に立って演技をしている。このとき、舞台がなければ俳優は「俳優」にはなれない。それはただの一人の男(女)に過ぎない。演じる場としての舞台があるからこそ、彼(女)は「俳優」になれる。同じことは舞台にもいえる。舞台もまた、俳優がいなければ「舞台」にはなりえない。俳優のいない舞台は、がらんとした平坦な空間でしかない。俳優が立ち、演技をすることで、舞台ははじめて「舞台」たりえる。つまり、俳優と舞台は同時に存在しており、一方が消失すればもう一方も同時に消失するのです。
ハイデガーはこのような事態をさして、人間は「世界ー内ー存在」であるといっています。世界を抜きにして人間は存在できず、人間なくして世界は存在しないという意味です。
では、ハイデガーの議論は、凶悪犯罪のメカニズムを解明する認識論の探究とどう関連するのでしょうか?
結論的に言ってしまうと、私は、「世界ー内ー存在」の概念こそ、心理的要因と社会的要因が解きがたく入り混じった現象を解明する手がかりとなるのではないかと考えています。なぜなら、「私」と「世界」が同時に存在すると考えれば、個人の心の問題と社会の問題のどちらが先か、重要かといった不毛な問いは解消され、個々の一人称視点から見た世界(社会)の有り様を解明することが、そのまま社会全体の有り様を解明することと同義になるからです。
しかし、これは哲学であって科学ではないため、社会における具体的な実践に直接つながる意義を見いだすことは難しい。科学技術が発展し、人々の価値観にも科学的視点が浸透している現代において、人間観を科学と何らかの形で関連づけることは(学問として人間を研究する場合は)避けられないと思います。なぜなら、現代において科学と接点をもたない人間観は、宗教という形を取るしかなくなり、結局は人それぞれ好みの問題だという相対主義に帰着してしまうからです。だから、「世界ー内ー存在」概念に基づく存在分析を、何らかの形で科学(とりわけ心理学や社会学)と結びつけることが、凶悪犯罪のような、心理的要因と社会的要因が複雑に絡み合った現象の解明につながる道だと私は考えます。それは現在の学問分野であれば、「現象学的心理学」や「現象学的社会学」のような試みになるでしょう。ただし、「現象学的心理学」と「現象学的社会学」に区分しただけでは、心理と社会の二元論は結局解消されていないため、両者をどのように統合するかは、今後の私の課題だと考えております。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
脚注
(※1) G.H.ミードという社会学者は、人間の自我を、他者から見た客観的存在である「me」と、meに還元し尽くせない「この私」という主体的意識の「I」に分類しました。「私」という存在には、常に他者からの視線には収まりきらない残余部分とでもいうべきものがあるということです。自我は二重構造になっている。例えば、これを読んでくださっているあなたは勤め先では「上司」かもしれませんし、家庭では「父親(母親)」、実家では「息子(娘)」、レストランでは「客」かもしれません。これらのように他者の視線に規定された「私」の存在様式のことをmeといいます。でも、「私」というのは、上司や父親や息子や客といった役割に収まりきらない部分、役割を取っ払ってもなお「私」として残る、「ありのままの私」とでもいうような部分がある。それが「I」です。
東大刺傷事件の少年をミード風に理解するなら、社会のまなざし(これをミードは「一般化された他者(generalized others)」といっています)が少年の自我を「頭のいい子」「優秀な子」といったmeに切り詰めた結果、「I」としての少年の自我が自己喪失の危機に陥り、それを克服しようとして、少年がmeから「I」へ自我を取り戻そうとした結果、犯罪が引き起こされたということになるのではないでしょうか。
ミードは生前に本を出しませんでしたが、講義録が『精神・自我・社会』としてまとめられ、これが彼の実質的な主著となっています。みすず書房から邦訳が出ておりますので、興味のある方はお読みになるとよいと思います。
(※2)脇道にそれますが、「自己と社会の矛盾」というテーマは、現実社会の事件だけでなく、創作においても繰り返し現れてきたテーマだと思います。たとえば文学では、ドストエフスキーの『地下室の手記』やヘルマン・ヘッセの『車輪の下』、フランツ・カフカの『変身』、太宰治の『人間失格』等がそうだと思います。
映画ではマーティン・スコセッシ監督の『タクシードライバー』(1976)や長谷川和彦監督の『青春の殺人者』(1976)や『太陽を盗んだ男』(1979)等が当てはまると思います。
また、アニメーションでは、「新世紀エヴァンゲリオン」の主人公である碇シンジがエヴァに乗る意味に苦悩する場面がくり返し描かれていますが、これも自己の欲求と社会から押しつけられる規範の板挟みになる現代人の実存的危機を象徴していると思います。
(※3)見田の「社会のまなざし」に関する考察には、思想家ミシェル・フーコーが『監獄の誕生』で展開した、「権力こそが主体を構成する」という権力論と相通ずるものを感じます。しかも、「まなざしの地獄」が発表されたのは1973年ですが、これは『監獄の誕生』(1975)よりも2年早い。その点で見田の論考は世界レベルで見ても画期的ではないでしょうか。
参考文献
古東哲明(2002)『ハイデガー=存在神秘の哲学』講談社現代新書
見田宗介(2008)『まなざしの地獄―尽きなく生きることの社会学』河出書房新社
※本稿で使用した新聞記事の著作権は、河北新報社に帰属します。
