安倍元首相暗殺は「革命」か?―ソレル、ベンヤミンから考えるアナーキズム―
安倍晋三元首相
画像は首相官邸ホームページより引用:第98代 安倍 晋三 | 歴代内閣 | 首相官邸ホームページ (kantei.go.jp)
1.はじめに
皆さんもご存じの通り、2022年7月8日(金)、奈良市の近鉄大和西大寺駅前で、参院選の応援演説中だった安倍晋三元首相が銃撃され、死亡しました。殺人未遂容疑で現行犯逮捕された山上徹也容疑者は「世界平和統一家庭連合(旧・統一教会)に母親が入信し、家を破産させられたため団体に恨みがあった。安倍元首相が団体とつながりがあると思い、殺そうと思って犯行に及んだ。安倍氏の政治信条に対する恨みはない」と供述しています(本稿執筆時点、2022年7月22日)。
この事件に対して大手新聞社やマスメディアは一斉に非難の声を挙げました。以下、事件翌日の主要な全国紙5紙(朝日・読売・毎日・産経・日経新聞)の論説の見出しを列挙します。
朝日「民主主義の破壊許さぬ」(2022年7月9日付朝刊1面)
読売「卑劣な言論封殺 許されぬ」(2022年7月9日付朝刊1面)
毎日「民主主義への愚劣な挑戦」(2022年7月9日付朝刊1面)
産経「卑劣なテロを糾弾する」(2022年7月9日付朝刊1面)
日経「許されざる蛮行」(2022年7月9日付朝刊1面)
ご覧の通り、大手新聞社は皆一様に本事件を「民主主義の根幹を揺るがす暴挙」だと非難し、「どんな理由や主張があっても暴力は許されない」と糾弾しています。
また、事件を受けて当日岸田首相は「民主主義の根幹たる選挙が行われている中、卑劣な蛮行が行われた。断じて許されない。もっとも強い言葉で非難する。決して暴力には屈しない」とコメントしました。
岸田文雄首相
画像は首相官邸ホームページより引用:第100代 岸田 文雄 | 歴代内閣 | 首相官邸ホームページ (kantei.go.jp)
TwitterやYahoo!ニュース等インターネット上においても、事件当日私が観察した限り、多くの驚愕、憤り、悲しみを表するコメントが見られました。
これらのことから、「民主主義の根幹は自由な言論にあり、どんな理由があっても暴力で自らの主張を押し通そうとすることは決して許されない」という価値観は、日本社会の共通認識として広く定着しているといえるでしょう。
2.問題の所在
しかし、「どんな理由があっても暴力は許されない」という主張は一見当たり前のようでいて、実はよく考えるとおかしい。暴力が認められないなら、なぜ警察は市民を逮捕・拘留したり、場合によってはその場で射殺したりできるのか?裁判所はなぜ被告人を死刑に処することができるのか?あるいは、なぜ自衛隊が存在するのか?これらは全て人間を殺害する装備や権能を有している以上、暴力に他ならないではないか?「暴力は許さない」と非難する国家自身が暴力を行使し、その声に同調する社会も―死刑や自衛隊には賛否両論あるとはいえ―国家が暴力を行使する現実を認識・追認しているではないか?・・・・・・。
これらのことから、国家は、実は無条件に暴力を否定しているわけではなく、国家が認めている暴力と認めていない暴力が存在することがわかります。
では、「認められている暴力」と「認められていない暴力」の違いは何でしょうか?それらは「暴力」という一語でくくれるものなのでしょうか?もしくくれないとしたら、そもそも「暴力」とは一体何でしょうか?歴史的に、「暴力」概念は「国家」と密接に結びつけて考察されてきました。「暴力」概念を考えることで、国家の本質が浮き彫りになるのではないでしょうか。国家の本質が矛盾をはらむものであれば、そこから国家を超克する可能性を考えることに繋がりうるのではないでしょうか。
そこで本稿では、前述の安倍元首相銃撃事件を受けて、国家と暴力の関係について考察することを試みます。まず「暴力」概念が思想史においてどのように検討されてきたかを概観し、とりわけドイツの思想家ベンヤミンの暴力理論に着目します。著作『暴力批判論』の読解を通して、現代社会における国家の廃絶―つまり革命―の可能性を考察します。
なお、容疑者の素性や犯行動機については、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)との関係が連日報道で取りざたされています。しかし本稿執筆時点(2022年7月22日)で以前明らかになっていない点が多いこと、また本稿のテーマと必ずしも関係する部分ではないことから、本稿においては容疑者の素性や犯行動機には深く言及しないことにします。
3.本論
本論では、「暴力」概念を考察した二人の思想家を取り上げ、「暴力」概念が歴史的にどのように構想されてきたかを分析します。
まず、「暴力」を体系的に考察した先駆者として、思想家のソレルを取り上げます。次に、ソレルの理論を批判的に発展させた思想家であるベンヤミンを取り上げ、著作『暴力批判論』の詳細な読解を通してベンヤミンの暴力理論の内容を明らかにします。
3-1.ソレルの暴力論
近代以降の社会において「暴力」を体系的に考察した最初の人物は、フランスの思想家ジョルジュ・ソレル(Georges Sorel, 1847~1922)です。
ジョルジュ・ソレル
画像はWikipediaより引用:ジョルジュ・ソレル - Wikipedia
ソレルは主著『暴力論』において、暴力を「フォルス」(force)と「ヴィオランス」(violence)の2種類に分けました。フォルスとはいわゆる物理的暴力のことで、私達が日常的に用いる、殴ったり蹴ったり殺したりする暴力です。これに対してヴィオランスとは、説明が難しいのですが一言でいうと、人間の生を昂揚させる激烈な力のことです。
ソレルの『暴力論』を翻訳した社会哲学者の今村仁司は、ソレルのヴィオランス概念を以下の6つに分類しています(塚原, 2008)。
(1)意志としてのヴィオランス(生の飛躍、激しく充実して生きようとする意志)
(2)行動の中でのみ生きる観念としてのヴィオランス(「神話」、ホメロス的叙事詩)
(3)創造する力としてのヴィオランス(「自由な人間」を創造する力、努力)
(4)モラルとしてのヴィオランス(自己犠牲、献身、ヒロイズム)
(5)労働あるいは生産としてのヴィオランス(生命の飛躍の先鋭的表現としての労働)
(6)徳(vertu)としてのヴィオランス(革命的ゼネストで発揮される人間的徳=勇気)
ここで上記の分類を全て覚える必要はありません。ただ、重要なのは、我々が一般的に暴力と呼んでいる暴力=フォルス(物理的暴力)とは異なる暴力概念(ヴィオランス)をソレルが構想していたということです。
ソレルの生きた19世紀フランス社会は、イギリスから産業革命が波及したことで、生産様式としての機械が改良・発展し、資本主義が成長段階を迎えていました。その反面、富や資本を有する資本家階級(ブルジョワジー)と、自らの労働力以外に資本を持たない労働者階級(プロレタリアート)の格差が拡大し、両者が政治的に鋭く対立していました。このような社会においてソレルは、ブルジョワジーの道徳的堕落を糾弾し、労働者達のゼネラル・ストライキ(ゼネスト)(脚注※1)によって革命を起こして国家を転覆させ、腐敗した社会を道徳的に救済しようと考えました。ソレルの暴力理論は、国家が既存の秩序を強制的に維持しようとする暴力(フォルス)に対して、高度に規律された革命的労働者達のゼネストという暴力(ヴィオランス)によって対抗しようとするものでした。
一言で言えば、ソレルの暴力理論は「革命」の理論だったのです。
ソレルの暴力理論は、国家なき社会を目指そうとする点で、いわゆるアナーキズム(anarchism, 無政府主義)の思想に連なるものでした。
3-2.ベンヤミンの暴力論
ソレルは物理的暴力(フォルス)に対抗する暴力としてのヴィオランス概念を提起し、物理的暴力概念とは異なる新たな暴力概念の研究の境地を開拓しました。
このソレルの暴力論を批判的に継承し独自の暴力理論を展開したのが、ドイツの思想家ヴァルター・ベンヤミン(Walter Benjamin, 1892~1940)です。
ヴァルター・ベンヤミン
画像はWikipediaより引用:ヴァルター・ベンヤミン - Wikipedia
ベンヤミンは著作『暴力批判論』において、暴力と、法および正義の関係を考察しました。
以下の節では『暴力批判論』を詳細に読解することで、ベンヤミンの暴力理論を分析します。
流れとしては、まず暴力と法の関係に焦点をあてます。暴力が法によって排除されるのは、暴力が法の目的に反しているからではなく、暴力が法の外にあるということそれ自体によって法をおびやかすものであるからだということを指摘します。暴力が法の外にあることによって法をおびやかすのは、暴力が「法措定的機能」と「法維持的機能」(後述)をもっているからであり、それら二つの機能をあわせもつ「神話的暴力」(後述)が法としての国家を根拠づけていることを明らかにします。そして、神話的暴力に対立する暴力として「神的暴力」(後述)という暴力が存在し、ベンヤミンはこれによって神話的暴力を破壊し国家を廃絶しようとするアナーキズム(anarchism, 無政府主義)的な革命思想を唱えていたということを示します。
3-2-1.暴力と法の関係
まずベンヤミンは暴力と法の関係を考察します。法秩序において最も基本的な関係は、目的と手段の関係であり、暴力はさしあたって手段の領域に関わる問題だといいます。
まず法の概念についていえば、あらゆる法秩序のもっとも根底的で基本的な関係は、明らかに、目的と手段との関係である。そして暴力は、さしあたっては目的の領域にではなく、もっぱら手段の領域に見いだされる。
ヴァルター・ベンヤミン(1994)『暴力批判論 他十篇』岩波文庫 p29
しかし、暴力が手段において考察されるからといって、目的が正しければ手段は正当化されるのだという考えをベンヤミンは退けます。こうした見方からは、手段としての暴力それ自体を倫理的に批判する見地が失われてしまうからです。
ベンヤミンは法を「自然法」と「実定法」に区別します。自然法の視点では、目的が正しいかどうかだけが問題となり、正しい目的のためなら暴力が手段として用いられることも何ら問題とはなりません。それに対して実定法の視点では、適法な手段で法が実行されているかだけが問題となり、適法な手段で法が実行されてさえいれば、自動的に法の目的も正しいのだとみなします。
このように、一見すると視点が対照的な「自然法」と「実定法」ですが、ベンヤミンは両者に共通のドグマがあることを指摘します。それは、「正しい目的は適法の手段によって達成され、適法の手段は正しい目的へ向けて適用される」というドグマです。
(・・・)二つの学派は共通の基本的ドグマをもつことにおいて一致する。すなわち、正しい目的は適法の手段によって達成されうるし、適法の手段は正しい目的へ向けて適用されうる、とするドグマである。自然法は、目的の正しさによって手段を「正当化」しようとし、実定法は、手段の適法性によって目的の正しさを「保証」しようとする。
ヴァルター・ベンヤミン(1994)『暴力批判論 他十篇』岩波文庫 p31
そしてすぐ続けてこう指摘します。
もしこの共通のドグマ的な前提が誤謬であって、一方の適法の手段と他方の正しい目的とがまっこうから相反するとすれば、解決のできない二律背反が生まれるだろう。しかしこの点を明晰に認識するためには、まず圏外へ出て、正しい目的のためにも適法の手段のためにも、それぞれ独立の批評規準を提起しなくてはなるまい。
ヴァルター・ベンヤミン(1994)『暴力批判論 他十篇』岩波文庫 p31~32
つまりどういうことかというと、自然法も実定法もともに、目的は手段によって正当化され、手段は目的によって保証される。目的と手段は循環論法になっている。だから適法の手段と正しい目的がぶつかり合ったとき、法はそれ自体で自身を根拠づけることが出来なくなる。その二律背反を解消するためには、一度目的と手段の循環論法から視点をずらして、目的と手段を根拠づける独立の規準を探しましょう、という意味です。
結局ベンヤミンが言いたいことは、「法は結局、自分の存在を自力で根拠づけることができないから、法を根拠づける規準を探そう」ということです。
では、法の目的と手段を根拠づける独立の規準とは何か。
ベンヤミンは、実定法理論が暴力の種類を区別していることに注目します。その区別とは「歴史的に承認された暴力、いわゆる法定の暴力」と「法定ではない暴力」です。『暴力批判論』においては、この区別を素朴に適用するのではなく、そもそもこの区別が表している意味は何なのかを批判的に吟味することが課題だとベンヤミンは述べます。そして以下のように指摘します。
適法な暴力と不法な暴力とを区別することの意味は、自明ではない。その意味は、正しい目的のための暴力と不正な目的のための暴力とを区別するところにある、とする自然法的な誤解は、きっぱりとしりぞけられねばならぬ。むしろ実定法は、さきに言及したとおり、あらゆる暴力から、それぞれの歴史的起原についての、つまりなんらかの条件のもとでその暴力が得てきた適法性ないし承認の、証明書を要求するわけなのだ。法的暴力の承認は、具体的には、その目的への原則的に無抵抗の服従としてあらわれるから、暴力を仮りに区別する理由は、その目的の普遍的・歴史的な承認の存在、あるいは欠如、として基礎づけられる。この承認を欠く目的を自然目的と呼び、他を法的目的と呼んでおこう。
ヴァルター・ベンヤミン(1994)『暴力批判論 他十篇』岩波文庫 p33
持って回った言い方ですが・・・。法定の暴力と法定ではない暴力の区別は自明ではない。自然法の、目的が正しいか正しくないかで区別する考え方では、先述した循環論法に戻ってしまう。実定法は暴力を、その暴力が歴史的に得てきた適法性や承認によって区別する。この承認がない目的を「自然目的」とよび、承認がある目的を「法的目的」と呼ぶ。自然目的に基づいた暴力と法的目的に基づいた暴力があるんだということです。
さて、現代ヨーロッパにおいて、個人が自然目的に基づいてふるう暴力は、必ず国家の法的目的に基づいた暴力(法的暴力)と衝突せざるをえないとベンヤミンはいいます。そして国家の法的暴力は、個人の自然目的に基づいた暴力が目的を達成しようとする領域において、まさに法的暴力だけが目的を達成しようと迫ってくる。それはつまり、法は個人の手にある暴力を、法秩序をくつがえしかねない危険と見なしているということになります。そして、以下の重要な指摘をします。
(・・・)個人と対立して暴力を独占しようとする法のインタレストは、法の目的をまもろうとする意図からではなく、むしろ、法そのものをまもろうとする意図から説明されるのだ。法の手中にはない暴力は、それが追求するかもしれぬ目的によってではなく、それが法の枠外に存在すること自体によって、いつでも法をおびやかす。
ヴァルター・ベンヤミン(1994)『暴力批判論 他十篇』岩波文庫 p35
法の目的をまもろうとするならば、法の目的に反する暴力だけを排除すればいい。しかしそうではない。暴力は法の目的に反しているから排除されるのではなくて、法の外に存在すること自体によって排除されるということです。
3-2-2.暴力の二重の機能 ―法措定的機能と法維持的機能―
しかし、暴力が法の外にあるというだけでは、法が暴力をそれほどまでに恐れる理由は判然としません。なぜ、法は暴力を無視できないのでしょうか?
ベンヤミンはこの問いに、「それは暴力がある機能をもつからだ」と答えています。
その機能とは何か。それは「法を措定する」機能です。
(・・・)国家がストライキにおいて何よりも怖れているものは、暴力のもつある機能であって、その機能の探究をこそこの論文は、暴力批判の基礎、唯一の確実な基礎としようとしている。(・・・)それは、法関係を確定したり修正したりすることができる(・・・)。
ヴァルター・ベンヤミン(1994)『暴力批判論 他十篇』岩波文庫 p37~38
同様のことを以下のようにも言い表しています。
手段としての暴力はすべて、法を措定するか、あるいは法を維持する。二つの客語のいずれをも要求しないような暴力は、みずから効力を抛棄しているのだ。
ヴァルター・ベンヤミン(1994)『暴力批判論 他十篇』岩波文庫 p45
暴力は、暴力として振るわれるまさにそのことによって、新たな法を打ち立てる(措定する)。暴力は振るわれることによって法措定的暴力となる。暴力が法にとってかわる。そういう性格を暴力はもつ、ということです。
さらにベンヤミンは、法を措定する機能に関連して、暴力には法を維持する機能もあると主張しました。ベンヤミンはこの機能を、国家が兵役義務によって若者を強制的に徴兵する現象に見いだしています。
要するに大事なことは、暴力は「法措定的機能」と「法維持的機能」の二重の機能をもっているということです。
ここで、先にベンヤミンが立てていた問いを思い出していただきたい。ベンヤミンは、法は自力で自分の存在を根拠づけることが出来ないことを指摘し、法を根拠づける規準を探す必要があることを主張していました(前節参照)。ではその規準とは何なのか。ここに至ってベンヤミンはこの問いに答えます。
法の根源は暴力である。暴力が法を措定し維持する。本質的に法と暴力は同じものだ。それがベンヤミンの回答です。
つまり暴力が、運命の冠をかぶった暴力が、法の根源だとすれば、暴力が法秩序のなかに現出するときの最高の形態である生死を左右する暴力となって法の根源が代表的に実体化され、怖るべきすがたをそこに顕示していることは、想像するにかたくない。
ヴァルター・ベンヤミン(1994)『暴力批判論 他十篇』岩波文庫 p42~43
上の引用でも言及されているとおり、ベンヤミンは死刑制度の存在こそ暴力が法の根源であることをもっとも如実に示していると指摘します。
3-2-3.「神話的暴力」
前節までの内容をおさらいすると、暴力は法の目的に反しているから排除されるのではなく、法の外にあることそれ自体が原因で排除されるという話をしました。そしてそれは何故かというと、暴力が「法措定的機能」と「法維持的機能」という二重の機能をもっているからでした。このことからベンヤミンは、暴力こそが法の根源であると主張したのでした。
ここでベンヤミンは彼特有の謎めいた言葉を生み出します。彼は「法措定的機能」と「法維持的機能」を合わせもつ暴力を一括して、「神話的暴力」と名付けたのです。
神話的暴力という呼称は、ギリシア神話のニオベ伝説に由来します。
いわく、昔テーバイにはニオベという女性がいて、多くの子だからに恵まれました。自らの幸運に夢中になったニオベは、あるとき女神レトの前で、自分の子どもの数を自慢しました。また、アポロンとアルテミスの姿を馬鹿にして、「私の子ども達のほうが彼らよりも優れている」などと吹聴しました。怒った女神レトは、アポロンとアルテミスに頼んで、ニオベの子ども達を全員殺させてしまいました。ニオベは悲しみのあまり、ゼウスに頼んで石に姿を変えられました。
なぜベンヤミンは、唐突にニオべ伝説を持ち出したのでしょうか?それは、この神話に法と暴力の本質が示されていると洞察したからです。以下長いですが引用します。
たしかにアポロとアルテミスの行為は、ただの処罰行為と見えるかもしれないが、しかしかれらの暴力は、ある既成の法への違反を罰するというよりは、むしろひとつの法を設定するものなのだ。ニオベの不遜が禍いを招くのは、それが法を侵すからではなくて、運命を挑発するからにほかならない。挑発されたこの闘争において、運命はぜがひでも勝ち、勝って初めてひとつの法を出現させる。こういう古代的な意味での神々の暴力が、刑罰の持つ法維持的な暴力とどれほど違うかを、英雄伝説はしめしている。(・・・)ところで、暴力は不確定で曖昧な運命の領域から、ニオベにふりかかる。この暴力はほんらい破壊的ではない。それはニオベの子らに血みどろの死をもたらすにもかかわらず、母の生命には手を触れないでいる。ただしこの生命を、子らの最期によって以前よりも罪あるものとし、だまって永遠に罪をになう者として、また人間と神々とのあいだの境界標として、あとに残してゆくのだ。もし神話的宣言としてのこの直接的な暴力が、法措定の暴力の親類だと、そればかりか同一物だという証明がなされるなら、問題性は、この暴力から法措定の暴力へ(・・・)はねかえる。同時にこの関連は、あらゆる場合に法的暴力の根底に存在する運命へ、より多くの光を投げかけ、法的暴力の批判を大幅に進展させることを、約束する。すなわち、法措定における暴力の機能は、つぎの意味で二重なのだ。たしかに法措定は暴力を手段とし、法として設定されるものを目的として追求するのだが、しかしその目標が法として設定された瞬間に暴力を解雇するわけではなく、いまこそ厳密な意味で、しかも直接に、暴力を(・・・)法措定の暴力とする。法の措定は権力の措定であり、そのかぎりで、暴力の直接的宣言の一幕にほかならない。正義が、あらゆる神的な目的設定の原理であり、権力が、あらゆる神話的な法措定の原理である。
ヴァルター・ベンヤミン(1994)『暴力批判論 他十篇』岩波文庫 p55~57
何を言っているのかよく分かりませんが、要するに、アポロンとアルテミスの暴力こそ、法措定的暴力の起原だということです。ニオベは罪深いことをしたから罰されたのではなく、アポロンとアルテミスから暴力をふるわれるというまさにそのことによって、罪深いものとなる。このことはベンヤミンによれば、法措定的暴力が二重の機能を持っていることを表している。法措定は暴力を手段として法措定を達成するのだが、法措定の目的が達成された後も暴力はなくならず、暴力それ自体が法措定的暴力として永続する。そういうことをベンヤミンは言っています。
3-2-4.「神的暴力」
前節において、ベンヤミンが「法措定的機能」と「法維持的機能」を含む暴力を一括して「神話的暴力」と呼んだという話をしました。神話的暴力が法を根拠づけているわけです。
では、ベンヤミンは神話的暴力を肯定的に捉えていたのでしょうか?実は、そうではありません。ベンヤミンは、端的にいって神話的暴力は腐敗してきている、と考えていました。それはなぜかというと、法的制度が自らの成立背景に暴力を存在させていたことを忘却してきているからだといいます。ベンヤミンによれば、ある法的制度がその成立に暴力を潜在させていることを忘れてしまうと、その制度は没落してしまいます。とりわけ、当時のドイツ議会を念頭に、暴力の法措定的機能が著しく衰退していることを批判しています。
ある法的制度のなかに暴力が潜在していることの意識が失われれば、その制度はかえって没落してしまう。現在では議会がその一例だ。議会は、かつて自己を成立させた革命的な力を忘れてしまったので、周知のみじめな見世物となっている。(・・・)議会には、そこに代表されている法措定の暴力についての感覚が欠けている。(・・・)すぐれた議会があることは比較的にのぞましいことでもあり、喜ばしいことでもあるだろう。だがそうはいっても、原理的に非暴力的な政治的合意の手段を論ずるときに、議会主義を持ち出すことはできない。なぜなら、議会主義が生きた諸問題のなかで何に到達するかといえば、それは起原にも終末にも暴力をまといつかせた、あの法秩序でしかありえないのだから。
ヴァルター・ベンヤミン(1994)『暴力批判論 他十篇』岩波文庫 p46~47
フランス革命やドイツ統一をはじめ、歴史を振り返れば議会は本質的に暴力的な代物である。それを忘れて、自らを非暴力的な紛争解決手段だと思い込んだ議会は衰退するんだ、ということをベンヤミンは言っています。
またベンヤミンは、神話的暴力の権化のような存在として、警察を挙げています。警察は「安全のため」など何かと理由をつけて、市民生活に干渉し、人々の自由を抑圧します。それは警察やそれを根拠づけている法の強さを表しているように見えるが、そうではない。むしろ法措定的機能と法維持的機能を併せ持つ暴力としての法が、衰退し、他者の暴力に対抗できる自信を失っていることの裏返しだとベンヤミンはいいます。
この二種類の暴力[筆者注:法措定的暴力と法維持的暴力のこと]は、死刑におけるよりももっと不自然に結合して、いわばお化けめいた混合体となって、近代国家の別の一制度である警察のなかに、現存している。(・・・)こういう官庁の非道さは、わずかなひとびとには感得されているが、それというのも、それが権限をも逸脱して粗暴きわまる干渉をおこない、繊細な領域へも盲目的に泥足をつっこみ、法律では国家に従属させえない知的なひとびとを取り締まることを、許されているからだ。(・・・)警察の「法」が根本において表示しているのは、国家が、なんとかして押し通したい具体的目的を、無力からか、(・・・)もはや法秩序によっては保証しえなくなっているところ、まさにそのところにほかならない。だから警察は、明瞭な法的局面が存在しない無数のケースに「安全のために」介入して、生活の隅々までを法令によって規制し、なんらかの法的目的との関係をつけながら、血なまぐさい厄介者よろしく市民につきまとったり、あるいは、もっぱら市民を監視したりする。
ヴァルター・ベンヤミン(1994)『暴力批判論 他十篇』岩波文庫 p43~44
このように、法が没落すると、それは議会の衰退や警察による市民生活への過度な干渉となって現れ、人々にとって有害な影響をもたらす。その現象の根本には神話的暴力の腐敗・衰退という事実があるというのがベンヤミンの考えでした。
では、腐敗し、衰退してきている神話的暴力に対して、我々はどう対処すればいいのでしょうか?
結論からいうと、ベンヤミンは神話的暴力を滅ぼすべきだと主張しました。そして、神話的暴力へ対抗する暴力としてベンヤミンは「神的暴力」という概念を提唱します。
「神的暴力」の概念は、神話的暴力の概念と比べて極めて難解です。分かりやすく説明することが難しいので、以下、ベンヤミンの定義をそのまま引用します。
直接的暴力の神話的宣言は、より純粋な領域をひらくどころか、もっとも深いところでは明らかにすべての法的暴力と同じものであり、法的暴力のもつ漠とした問題性を、その歴史的機能の疑う余地のない腐敗性として、明確にする。したがって、これを滅ぼすことが課題となる。まさにこの問題こそ、究極において、神話的暴力に停止を命じうる純粋な直接的暴力についての問いを、もういちど提起するものだ。いっさいの領域で神話に神が対立するように、神話的な暴力には神的な暴力が対立する。しかもあらゆる点で対立する。神話的暴力が法を措定すれば、神的暴力は法を破壊する。前者が境界を設定すれば、後者は限界を認めない。前者が罪をつくり、あがなわせるなら、後者は罪を取り去る。前者が脅迫的なら、後者は衝撃的で、前者が血の匂いがすれば、後者は血の匂いがなく、しかも致命的である。
ヴァルター・ベンヤミン(1994)『暴力批判論 他十篇』岩波文庫 p58~59
一読しただけでは、神的暴力がどのような暴力なのかさっぱり分かりません。ここからかろうじて分かることは、神話的暴力が法措定的機能を持っていたのに対して、神的暴力は法を破壊する。ニオベ伝説のように、神話的暴力は神と人間の境界線を引くものだったのに対して、神的暴力はそれを認めない。アポロンとアルテミスの暴力がニオベを罪深いものとしたように、神話的暴力は罪をつくるのに対して、神的暴力は罪を取り去る。神話的暴力が脅迫的に法の措定・維持を反復するものだったのに対して、神的暴力は「衝撃的」である。神話的暴力がそれによって人間の生命を奪うのに対して、神的暴力は生命を奪わない、しかし「致命的」である。こうした特徴を持つ、神話的暴力とは全く別種の暴力として「神的暴力」が存在するということです。
神話的暴力と神的暴力それぞれの特徴を表にすると、以下のようになります。
| 神話的暴力 | 神的暴力 |
| 法を措定する | 法を破壊する |
| 境界を設定する | 限界を認めない |
| 罪をつくり、あがなわせる | 罪を取り去る |
| 脅迫的 | 衝撃的 |
| 血の匂いがする | 血の匂いがなく、致命的 |
神話的暴力がギリシア神話のニオベ伝説を由来に名付けられた概念であるのに対して、神的暴力は旧約聖書の逸話から名付けられた概念です。その逸話とは旧約聖書民数記十六章の「コラの反逆」という逸話です。この逸話は、モーセと祭司アロンがイスラエル人を引き連れてエジプトを脱出し約束の地カナンへ向かう道中、コラという人物が民衆を扇動してモーセとアロンに反抗したという物語です。最終的にコラと取り巻きの民衆は神の怒りを買い、足下の大地が引き裂かれて生きたまま地獄に落とされました。
ベンヤミンは詳しく述べていませんが、この逸話には神の暴力の性質がよく表れているとのことです。
それはともかく、依然として神的暴力とは何なのかハッキリしません。もう少しベンヤミンの言を聞いてみましょう。
この神的な暴力は、宗教的な伝承によってのみ存在を証明されるわけではない。むしろ現代生活のなかにも、少なくともある種の神聖な宣言のかたちで、それは見いだされる。完成されたかたちでの教育者の暴力として、法の枠外にあるものは、それの現象形態のひとつである。したがってその形態は、神自身が直接にそれを奇蹟として行使することによってではなく、血の匂いのない、衝撃的な、罪を取り去る暴力の執行、という諸要因によって―究極的には、あらゆる法措定の不在によって―定義される。この限りで、この暴力をも破壊的と呼ぶことは正当だが、しかしそれは相対的にのみ、財貨・法・生活などにかんしてのみ、破壊的なのであって、絶対的には、生活者のこころにかんしては、けっして破壊的ではない。
ヴァルター・ベンヤミン(1994)『暴力批判論 他十篇』岩波文庫 p60
ここでベンヤミンは重要なことを言っています。神的暴力は神話や聖書など宗教的な伝承の中にだけあるのではなく、現代社会に住む私たちの生活の中にも見いだされる。それは例えば「完成されたかたちでの教育者」、これは私が思うに普通の学校の先生のことではなくて、宗教的指導者のような高度な魂を備えた人物のことだと思われますが、そういう人の暴力として法の枠外にあるものは神的暴力の現象形態のひとつである。したがって神的暴力の形態は、究極的にはあらゆる法措定の不在によって定義される。しかも神的暴力は財貨・法・生活に対してのみ破壊的であって、生活者、つまり普通の日常的生活を送る人々のこころに対しては破壊的ではない。
ベンヤミンは、最後に以下のように神話的暴力と神的暴力に言及することで、『暴力批判論』を締めくくっています。
(・・・)法維持の暴力はかならずその持続の過程で、敵対する対抗暴力を抑圧することをつうじて、自己が代表する法措定の暴力をもおのずから、間接的に弱めてしまう(・・・)。このことは、新たな暴力か、あるいはさきに抑圧された暴力かが、従来の法措定の暴力にうちかち、新たな法を新たな没落にむかって基礎づけるときまで、継続する。神話的な法形態にしばられたこの循環を打破するときにこそ、いいかえれば、互いに依拠しあっている法と暴力を、つまり究極的には国家暴力を廃止するときにこそ、新しい歴史的時代が創出されるのだ。神話の支配は、すでに現在、そこここで破れめを見せているのだから、新しい時代は、想像もつかないほど遠くへだたっているわけではないし、法に対抗する言葉も、無効ではあるまい。しかも法のかなたに、純粋で直接的な暴力がたしかに存在するとすれば、革命的暴力が可能であることも、それがどうすれば可能になるかということも、また人間による純粋な暴力の最高の表示にどんな名をあたえるべきかということも、明瞭になってくる。だが、ひとびとにとって、純粋な暴力がいつ、ひとつの特定のケースとして、現実に存在したかを決定することは、すぐにできることでもないし、すぐにしなければならぬことでもない。なぜなら、それとしてはっきり認められる暴力は、比喩を絶する作用力として現れる場合を除けば、神的暴力ならぬ神話的暴力だけなのだから。暴力のもつ滅罪的な力は、人間の眼には隠されている。純粋な神的暴力は、神話が法と交配してしまった古くからの諸形態を、あらためてとることもあるだろう。たとえばそれは、真の戦争として現象することもありうるし、極悪人への民衆の審判として現象することもありうる。しかし、非難されるべきものは、いっさいの神話的暴力、法措定の―支配の、といってもよい―暴力である。これに仕える法維持の暴力、管理される暴力も、同じく非難されねばならない。これらにたいして神的な暴力は、神聖な執行の印章であって、けっして手段ではないが、摂理の暴力ともいえるかもしれない。
ヴァルター・ベンヤミン(1994)『暴力批判論 他十篇』岩波文庫 p63~65
私が理解できた範囲で分かりやすく言い直してみます。
法維持的暴力は敵対する暴力を抑圧することで、かえって自らの法措定的暴力を弱めてしまう。それは神的暴力が従来の法措定的暴力、つまり神話的暴力を打ち破るときまで続く。神話的暴力、つまり究極的には国家暴力を廃止する時にこそ、新しい歴史的時代が始まる。神話的暴力は衰退してきているのだから、神的暴力が切り開く新しい時代はそんなに遠い時代ではない。しかし人々にとって、純粋な暴力、つまり神的暴力が歴史的にいつどこで実在したのかを決定することはすぐには出来ないし、しなければならぬことでもない。なぜなら、人々の目にはっきりと認められる暴力は、原則として神話的暴力だけだからだ。神的暴力は人間の眼には見えない。神的暴力は、神話が法と交配してしまった古くからの諸形態、つまり神話的暴力の形態に転化して現象することもありうる。しかし、非難されるべきものは、神話的暴力、つまり法措定的機能と法維持的機能をもった暴力である。
長いこと神的暴力について見てきましたが、私なりにやや乱暴に神的暴力の本質を要約してみます。
神話的暴力は法措定的暴力と法維持的暴力によって成っている。この神話的暴力が法としての国家を根拠づけている。これに対して神的暴力は、あらゆる面で神話的暴力と対立する暴力、つまり国家を廃絶する革命の暴力である。ベンヤミンは腐敗した神話的暴力を神的暴力によって打ち倒し、革命を起こして国家を廃絶するという思想、いわばアナーキズム(anarchism, 無政府主義)思想を提唱しているのだといえます。
というか、ある意味で神的暴力こそが革命そのものに他ならないのかもしれません。
3-2-5.『暴力批判論』の要約
以上にわたって、ベンヤミンの『暴力批判論』を詳細に分析してきました。次節でベンヤミンの暴力論を批判的に検討する予定ですが、その前にベンヤミンの暴力論の要点を箇条書きで簡潔にまとめておきます。
①暴力は法の目的に反しているから排除されるのではなく、法の外にあるということ自体によって排除される。それはなぜかというと、暴力が「法措定的機能」と「法維持的機能」を持っているからである。
②「法措定的機能」と「法維持的機能」をもった暴力を「神話的暴力」といい、この暴力が法としての国家を根拠づけている。
③神話的暴力にあらゆる面で対立する別種の暴力として「神的暴力」が存在する。これは神話的暴力を破壊し、国家を廃絶する革命的暴力である。ベンヤミンは神的暴力によって国家を廃絶しようとするアナーキズム的な革命思想を唱えている。
4.考察
考察では、前節において分析した内容をもとに、ベンヤミンの『暴力批判論』を批判的に検討します。とりわけ、「神的暴力」の概念を吟味することで、現代社会における革命のあり方を考察したいと思います。
4-1.神的暴力という謎
ベンヤミンによれば、「神的暴力」はあらゆる面で「神話的暴力」に対立する暴力として構想されていました。それは神話的暴力を滅ぼす暴力として提唱されていたのでした。
もう一度神的暴力の定義に関わる部分を引用します。
(・・・)神話的な暴力には神的な暴力が対立する。しかもあらゆる点で対立する。神話的暴力が法を措定すれば、神的暴力は法を破壊する。前者が境界を設定すれば、後者は限界を認めない。前者が罪をつくり、あがなわせるなら、後者は罪を取り去る。前者が脅迫的なら、後者は衝撃的で、前者が血の匂いがすれば、後者は血の匂いがなく、しかも致命的である。
ヴァルター・ベンヤミン(1994)『暴力批判論 他十篇』岩波文庫 p59
またこうも述べていました。
この神的な暴力は、宗教的な伝承によってのみ存在を証明されるわけではない。むしろ現代生活のなかにも、少なくともある種の神聖な宣言のかたちで、それは見いだされる。(・・・)その形態は、(・・・)―究極的には、あらゆる法措定の不在によって―定義される。
ヴァルター・ベンヤミン(1994)『暴力批判論 他十篇』岩波文庫 p60
そして『暴力批判論』の結びではこう述べています。
(・・・)ひとびとにとって、純粋な暴力がいつ、ひとつの特定のケースとして、現実に存在したかを決定することは、すぐにできることでもないし、すぐにしなければならぬことでもない。なぜなら、それとしてはっきり認められる暴力は、比喩を絶する作用力として現れる場合を除けば、神的暴力ならぬ神話的暴力だけなのだから。暴力のもつ滅罪的な力は、人間の眼には隠されている。
ヴァルター・ベンヤミン(1994)『暴力批判論 他十篇』岩波文庫 p64
ベンヤミンの神的暴力に関する説明は矛盾に満ちています。法が排除する暴力は法措定的機能と法維持的機能をもっている以上、法に対立する暴力は全て神話的暴力のはずです(法もまた神話的暴力に根拠づけられているのですが)。ところが神的暴力は法を措定するのではなく破壊する。神話的暴力は流血を伴うが神的暴力は流血を伴わない。にもかかわらず致命的である。神的暴力は宗教的な伝承の中だけに存在するのではなく、現代の我々の生活にも見いだされる。しかし眼には見えない。
・・・・・・。
率直に疑問を呈すると、こんな「暴力」が一体本当に存在するのでしょうか?ひとつだけ言えることは、神的暴力は私たちが一般に「暴力」ときいて思い浮かべる行為、例えば殴ったり蹴ったり破壊したり殺したりするような暴力とは全く異なった「暴力」であろう、ということです。にも関わらず、ベンヤミンによれば神話的暴力を滅ぼし、国家を廃絶するほどの力を秘めた暴力だというのですから、全く以てわからなくなります。
4-2.神的暴力を解釈する
本節では私なりに神的暴力を解釈してみます。
先に引用したとおり、ベンヤミンによれば「暴力の持つ滅罪的な力は、人間の眼には隠されている」、つまり神的暴力は人間の眼には見えないとのことでした。眼には見えないということは、神的暴力は人間の感覚器官では捕らえられないということです。つまり神的暴力は、人間の頭の中だけで思考することしかできない概念だということです。
これが意味することは何か。それは、「人間は神的暴力が本当に存在するのか、それとも存在しないのかを知ることはできない」ということではないでしょうか。
では、「神的暴力」という概念はベンヤミンの空想に過ぎないのでしょうか?それは人間の思考にとって何ら積極的価値をもたない概念なのでしょうか?
私は、そうは考えません。
私が思うに、神的暴力は人間の行為の価値をはかる「規準」として意味があるのです。
そもそもベンヤミンによって神的暴力という概念が要請されたのは何故だったでしょうか?それは腐敗した神話的暴力を滅ぼし、革命を起こして国家を廃絶するためでした。
しかし私はもう一歩踏み込んで考えたい。そもそも何のために、革命による国家の廃絶をしなければならないのでしょうか?
おそらくベンヤミンに言わせれば、「神話的暴力が人間の自由を抑圧しているから、人間が自由になるためだ」ということになるのでしょう。人間の自由が「目的」で、神的暴力=革命による国家の廃絶がその「手段」だというわけです。
では、何のために「自由」を求めるのか?
それは、突き詰めると、自由を得ることによって「幸福」な生を得るためでしょう。平たくいえば、幸せになるために自由を求めるんだということです。幸福が「目的」で、自由がその「手段」だというわけです。
こうしてみると、結局のところ、神的暴力=革命は人間の幸福という究極目的の手段だということがわかります。
しかし、この理屈はおかしい。当たり前のことですが、私たち人間はみな、ひとりひとり幸福を感じる対象が異なります。例えばある人は政治活動に参加してる時に幸福を感じるかもしれない。またある人は、自室でゲームをしている時に幸福を感じるかもしれない。そのまた別の人は、おいしいお菓子を食べているときに幸福を感じるかもしれない。さらに別の人は、ペットの犬や猫と遊んでいるときに幸福を感じるかもしれない、等々・・・。だから、ある人にとって幸福を感じる対象が、別の人にとっても幸福を感じる対象だとは限らないのです。
だから、神的暴力=革命を起こして国家を廃絶したとしても、それが必ずしも人々の幸福に繋がるとは限りません。それはせいぜい少数の政治的意識が高い人々の幸福を高めるだけかもしれないのです。むしろ多くの人々の生活を混乱させ、不幸にするおそれすらある。
しかるに、革命は国家全体の政治体制が一変する出来事なのだから、その国家の国民全員に関わる出来事です。国民全員に関わる出来事である革命を、ごく一部の人々の幸福のために起こすことは、果たして正当化できるのでしょうか?いやそもそも、一部の人々の幸福のために起こされる革命など、「革命」の名に値するでしょうか?
私が思うに、革命とはそんなものではない。革命は全国民に関わる出来事である以上、全ての人々に妥当する「道徳的普遍性」を持たなくてはならない。しかるに「幸福」を目的とすると、革命は道徳的普遍性を失ってしまう。ではどうすればいいのか?
革命が道徳的普遍性を保つには、革命を幸福という目的の「手段」として実行するのではなく、革命それ自体を「目的」として実行しなければならないと考えます。幸福のために革命をやるのではなく、革命のために革命をやるということです。
革命が全ての人々に妥当する道徳的普遍性をもつには、それが生む結果を一切考慮してはならない。革命が人々を幸福にするか・不幸にするかで革命の実行を判断してはいけない。革命は、それが革命であるがゆえになされなければならない。
私は急いで誤解を解かなくてはならないでしょう。私は、他人の都合なんか考えず好き勝手に暴力をふるって革命を起こせばいいと言っているのではありません。むしろ私は、一般的に思い浮かべられるような「暴力による革命」を完全に否定します。
なぜか。個人によって振るわれる有形の暴力―つまりソレルの物理的暴力(フォルス)ないしベンヤミンの神話的暴力―は、必ずある目的をもって振るわれます。その目的は色々あるでしょうが、突き詰めるとそれは結局「幸福」を得るという目的に帰着します。幸福を目的としている以上、有形の暴力は決して道徳的普遍性をもつことができません。道徳的普遍性を持たない暴力はその時点で「革命」とは呼べないのです。それは「犯罪」でしかない。
革命の暴力はただの暴力ではなく、「神的暴力」であることを思い出してください。それはいかなる実力行使も伴わない「暴力」です。ベンヤミンの言を借りれば「血の匂いがなく、しかも致命的」で、国家を廃絶する暴力、それが神的暴力です。
4-3.結局「神的暴力」とは何なのか?
長々と論じてきましたが、結局、神的暴力とはどういう行為を指すのでしょうか?本節では私なりに神的暴力の考察に結論を出してみます。
神的暴力とは何か。それは、人間には分からないのです。人間は神的暴力を認識することはできません。人間は神的暴力を思考することしかできないのです。
人間にできるのは、自らの行為が神的暴力である「かのように」行為することだけなのです。神的暴力とは認識の対象ではなく、行為の価値基準なのです。
ベンヤミンによれば、腐敗した神話的暴力を破壊し、国家を廃絶する暴力=革命として、神的暴力があるのでした。ベンヤミン自身、ついにこの暴力を具体的に明示することはありませんでした。我々はベンヤミンの遺したわずかな記述を手がかりに、自分が神的暴力だと考えた行為をするしかないのです。しかもそれは好き勝手に神的暴力を考えればいいというわけではありません。先にもくり返したように、革命は全ての人々に妥当する道徳的普遍性をそなえていなくてはならない。だから道徳的普遍性と合致するように神的暴力=革命を考え、行為しなくてはなりません。
私達がする/した行為が、真実として神的暴力かそうでないかは問題ではありません。それは人間には知り得ないことだからです。語弊があるかもしれませんが、私達は人間の立場で思考しうる神的暴力を行えばそれでいいのです。もし国家の廃絶がありうるとすれば、その積み重ねの上にしかないのです。ただし前述の通り、少なくとも物理的暴力ないし神話的暴力による自称・革命は、革命の名に値しない犯罪行為であることは断言します。
以上述べた私の思想的立場を、私は「道徳的アナーキズム」(moral anarchism)と名付けます。物理的暴力(フォルス)や神話的暴力ではなく、道徳的普遍性をそなえた神的暴力によって国家廃絶を目指す。それが私の思想的立場です。(脚注※2)
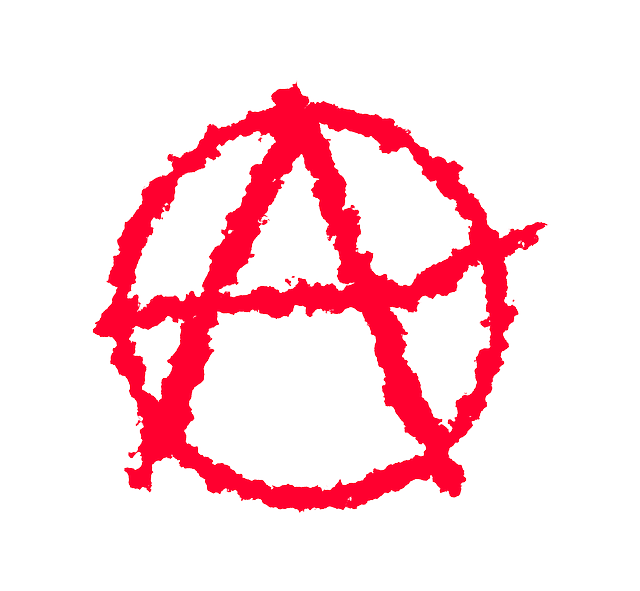
5.おわりに
安倍晋三元首相
画像は首相官邸ホームページより引用:第98代 安倍 晋三 | 歴代内閣 | 首相官邸ホームページ (kantei.go.jp)
最後に、冒頭の安倍元首相銃撃事件に立ち返り、本稿で試みた暴力の考察を踏まえて、私の本事件に対する若干の考えを述べて結びとします。
私は、今回の安倍元首相暗殺は、いかなる意味でも革命とはいえないと考えます。
山上容疑者は、「世界平和統一家庭連合(旧・統一教会)に母親が入信し、家を破産させられたため団体に恨みがあった。安倍元首相が団体とつながりがあると思い、殺そうと思って犯行に及んだ」と供述しています(本稿執筆時点、2022年7月22日)。つまり、旧・統一教会への自らの恨みを晴らすために安倍元首相を殺害したわけです。これは図式的に言うと、自らの恨みを晴らすという目的の手段として安倍氏を殺害したということです。それは結局恨みを晴らすことで自らが幸福を得るためになされた行為だったといえます。幸福を目的にした行為である以上、山上容疑者の行為は決して道徳的普遍性を持つことはできません。その意味で山上容疑者の行為は革命の名に値しないといえるでしょう。(脚注※3)
また、山上容疑者の放った銃弾は、いかなる意味でも「神的暴力」ではありませんでした。銃弾は法を何ひとつ破壊できなかった。銃弾はソレルのいう物理的暴力(フォルス)、あるいはベンヤミンのいう法措定的暴力でしかない。山上容疑者は銃撃の直後拘束され逮捕されたので、彼によって新たな法が措定されることもありませんでした。彼は今後、法に則った手続きで刑事裁判にかけられ、しかるべき刑事罰を受けることでしょう。そのプロセスには法の破壊というモーメントも、新たな法措定のモーメントも入り込む余地はない。今まで無限にくり返されてきた、国家の神話的暴力の反復があるだけです。
平たく言えば、今回の銃撃事件では国家は何も変わらないということです。
山上容疑者の行為は何ら革命的ではなかった。彼の暴力はただ野蛮で残忍な、犯罪です。そのような暴力からはいかなる革命の可能性も出てこない。
では、現代社会において革命がありうるとすれば、それはどのようになされるのでしょうか?
それは、「道徳的アナーキズム」に基づいた行為によってなされると私は考えます。自分の行為が常に神的暴力=革命であるかどうかを考慮し、自らの行為が道徳的普遍性をそなえた神的暴力=革命であるかのように行為する。その積み重ねの上に国家の廃絶がある。
これが現代社会において考えられる革命のかたちだと私は主張します。
最後に本稿で残された課題について一言しておきます。それは道徳的アナーキズムの実践において、神的暴力が実際にどのような形の行為によって具現化されうるのか、ついに明確に示せなかったことです。もとより神的暴力は人間が認識することができない「暴力」ですから、本来この問いに答えるのは不可能ですし、具体的な形をとった瞬間にそれはもう神的暴力ではないのだ、と言い逃れることもできなくはありません。そうはいっても、何かしら具体的な指針がなければ思想を実践することも難しいので、ここでひとつ、私が神的暴力になりうると考えているものを挙げてみます。
神的暴力になりうるもの。それはおそらく「言語」ではないかと私は考えています。なぜなら、人間が有形の行為を伴わずに現実にはたらきかける手段は、言語しかないと思われるからです。ただし、それはおそらくただの言語ではない―まして「言葉の暴力」や「ヘイトスピーチ」では断じてない―と思われます。神的暴力の最も重要な特徴は法を破壊する「暴力」であるということです。しかるに我々が日常的に用いる言語は常に法措定的・法維持的ではないでしょうか。
法を破壊する言語・・・・・・。それはなにか「呪文」のようなものではないか。いまの私に考えられるのはここまでです。この先の考察は今後の課題だと考えております。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
脚注
(※1)ゼネラルストライキとは、全国全産業の労働者が一斉にストライキを行うこと。ゼネスト。(広辞苑第七版)
(※2)哲学に多少なりとも詳しい方であれば、私の「道徳的アナーキズム」の思想が哲学者イマヌエル・カント(Immanuel Kant, 1724~1804)の批判哲学をもとに構想されたものであることはすぐにお気づきになったかと思います。だから本稿の副題はもともと「ソレル、ベンヤミン、カントから考えるアナーキズム」にするつもりだったのですが、カント哲学に言及する余裕が本稿にはなかったこと、カント哲学の難解な用語を用いない考察を試みたこと等から本文ではカントに言及しませんでした。
(※3)もとより山上容疑者は旧・統一教会への個人的な恨みによって犯行に及んだのであって、革命など起こそうとしたつもりではなかったでしょう。私が山上容疑者の犯行が革命たりえないことをことさら強調するのは、第一にいわゆる物理的暴力が決して革命の名に値しないただの犯罪であることを主張するためですが、それと同時に、安倍元首相が死去したことにわき立っている左翼や自称リベラルの幻想を打ち砕くためでもあり、また山上容疑者を英雄のように祭り上げる最近のネットにおける風潮に冷や水を浴びせるためでもあります。
文献
塚原史(2008) 「暴力論の系譜: 今村仁司とジョルジュ・ソレル」 東京経大学会誌(経済学) = The Journal of Tokyo Keizai University : Economics 259 83-94
ヴァルター・ベンヤミン(1994)『暴力批判論 他十篇』岩波文庫





