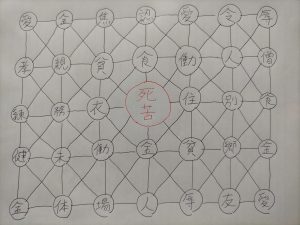哲学とは何か―「生哲」の提唱―
1.はじめに
私事だが、私が人生で哲学に触れてから、来年で10年になる。この間、私は古今の哲学書や文学を乱読し、様々な分野の学術書を読みふけり、多くの学問的知識を蓄えた。しかし、ある時それらの知識が不毛で私の人生にとって何の意味も持たないことを悟り、一度今まで学んできたことを全て捨て去って、一から自分自身の学問体系を築き上げようと決意した。そうして生まれたのが革生学であった。
私は自前の学問体系を提唱したのを機に、自分が10年かけて考え、実感したことの総括を試みたくなった。そこで本稿では、現時点で私が考える「哲学」とはどのようなものであるのか、従来の学説にとらわれず率直に自分の立場を提起し、私の10年にわたる思考の一区切りとしたい。
まず、哲学とは何かについて述べる前に、「哲学とは何でないか」について詳述する。「哲学」という言葉は一般的に乱用されているきらいがあり、哲学という言葉で指されているものが本来は哲学の名に値しないものであったり、哲学とは似て非なるものであったりする。そこでまず、哲学ではないものについて取り上げ、哲学という言葉のピントを絞り込む必要がある。哲学ではないものの代表として、本稿では①自己啓発②宗教③哲学史の3つを取り上げ、これらと哲学の差異を明確化する。キリスト教における否定神学が「神とは○○である」というのではなく、「神とは○○ではない」という命題を重ねることによって神の本質に迫ろうとしたように、「哲学とは○○ではない」という命題を重ねることで哲学の本質に近づく足がかりとしたい。
第3節では対照的に、「哲学は○○である」という積極的な命題によって、私の哲学観を率直に披瀝する。結論を先取りすれば、哲学とは「問いを生きること」である。
第4節では、哲学は「問いを生きること」だという主張を踏まえ、ある問いが哲学的な問いといえる条件を掘り下げる。これも結論を先取りすれば、哲学的問いである条件とは問いが①問いの固有性と②問いの普遍性を兼ね備えていることである。
第5節では、先の2つの条件を満たす問いは、実はたった一つしかない(厳密には二つだが、切り離すことができない一つの問いである)ことを主張する。それは「私とは何か、私はいかに生きるべきか」という問いである。これこそ全ての哲学が解こうとしてきた問いに他ならない。
最後の第6節では、これまで述べてきたことの見地からフィロソフィー(philosophy)の訳語としての「哲学」という言葉を再検討し、明治以来のこの訳語が、フィロソフィーの本質を十分に掴んでいないことを指摘する。そして、「哲学」という訳語に代わり、新たに「生哲」(せいてつ)という訳語を提唱する。なぜなら、哲学とは「問いを生きること」であって「学問」ではないからであり、「生哲」という言葉こそ、フィロソフィーの本質をより正確に表現できると考えるからである。
2.哲学ではないもの
本節では哲学でないものとして、①自己啓発②宗教③哲学史の3つを取り上げる。なぜこの三つなのかというと、私が見るところ、この三者が「本当は哲学とは異なるものなのに、世間で哲学と誤認・混同されているもの」の代表格だからである。
2.1.自己啓発は哲学ではない

いわゆる自己啓発書といわれるジャンルの書籍には、「○○の哲学」というタイトルのものが少なからず存在する。例えば「プロサッカー選手○○の哲学」や「経営哲学」といったようなものである。ちなみに本稿執筆時(2023年12月)は、メジャーリーガーの大谷翔平選手の大活躍を受けて、彼の愛読書とされている中村天風なる人物の『運命を拓く』という書籍―いわゆる「成功哲学」―がベストセラーになっている。
しかし、これらの内容は実際には「哲学」とは似て非なるものである。
「自己啓発」とは、当人が置かれている一定の環境―資本主義経済、会社・組織における自分の立場、仕事の内容、人間関係etc―を所与のものとして前提した上で、その環境自体に対しては批判や疑問を向けることなく、置かれた環境の中でいかに上手に、「幸福に」生きるかということに焦点を置き、その観点から性格や習慣を改造―実際は洗脳に近いが―する営みである。
自己啓発は人生について考え、何らかの実践を伴う営みであるはずである。にもかかわらず、自己啓発においては、「人間とは何か」「人間はいかに生きるべきか」という根本問題は棚上げされており、あくまでも当人が現状置かれている環境の中で、彼(女)がいかに上手に立ち回り、幸福に生きることができるかが主要な関心事になる。だから、自己啓発は徹底して現世的・世俗的な営みである。もっとも、自己啓発では神や魂や運命といったスピリチュアルな主題が取り上げられることも少なくない。その点では一見すると自己啓発は超・世俗的、観念的な印象を与える。しかし、自己啓発は神・魂・運命等の本質を解明することが目的なのではなく、あくまでも当人が現在置かれている人生を成功に導く思考の手段としてそれらの題材を取り上げているにすぎない。
哲学は自己啓発とは対照的である。哲学は、自己啓発においては所与の前提として問題にされない環境や社会制度、それを支えている常識や社会的通念等、ありとあらゆる前提を排して、虚心坦懐に「自分とは何か、自分はいかに生きるべきか」を問う営みである。自己啓発の文脈では当然視されるものを、哲学の文脈では疑い問い直す点に違いがある。
また、哲学は自己啓発と異なり、「幸福」を目的とした営みではない。哲学することで自分という存在や人生に対して得られた洞察は、必ずしも当人を幸福にしない。まして世俗的な成功を保証するものでもない。むしろ哲学することによって、深刻な懐疑に陥ったり、不幸な認識に到ることも大いにあり得る。しかし、どんなに不幸になろうと、どんなに常識的な見方に反しようと、自らの生が肌身で実感した真実を敢然と主張し、思考を突き進めていく点に哲学の本懐がある。自己啓発は社会的な営みであるが、哲学は反社会的な営みである。
言い換えると、自己啓発は「幸福」を目的とした営みであるが、哲学は「真・善・美」を目的とした営みである。たとえ不幸になるかもしれなくとも、真・善・美を追求していく姿勢を最後まで貫くのが哲学なのである。
2.2.宗教は哲学ではない
次に、哲学としばしば混同されるものとして「宗教」を取り上げる。宗教は神や魂といった、眼に見えないものを主題とするため、一見すると哲学との違いが分かりにくい。最近(2023年12月時点)ベストセラーになった書物に出口治明の『哲学と宗教全史』があるように、一般に哲学と宗教は同じジャンルに属する概念とみなされているのではなかろうか。
しかし、宗教も実は本質的な哲学との差異がある。
宗教が追求する目的は「真・善・美」であり、その点は哲学と共通である。しかし、それに到達するための手段が哲学と異なる。
宗教の根底にある心のはたらきとは「信仰」である。宗教体系の中には、たとえば「イエス・キリストは神の子である」だとか、「世界の終末の日に神の審判がくだり、神を信じる者は天国に、信じない者は地獄に行く」といった、合理的に説明できない事柄が核心にあることが多い。それら非合理的な命題のまとまり―「信仰体系」とでもいうべきか―を、思考を手放して全面的に「信じる」ことに、宗教の本質がある。
これに対して、哲学の本質は「思考」にある。合理的に説明できない一切の前提条件を排し、「○○は△△である」という命題に対して「本当にそうか?」と疑問を投げかけ、自分が納得できるまで問いを積み重ねることで真理に到達しようとする。この点は先に自己啓発との対比で述べたことと同じである。
宗教の基本単位が「信仰」であるのに対して、哲学の基本単位は「思考」である点に違いがあるといえよう。宗教と哲学は、「真・善・美」を目的とする(そして宗教はそれに到達することによって幸福を得る)点で共通しているが、宗教は信仰によって真・善・美に到達しようとするのに対して、哲学は思考によってそれに到達しようとする。
2.3.哲学史は哲学ではない
最後に、哲学ともっとも混同しやすいものとして「哲学史」を取り上げる。哲学と哲学史を混同する過ちは、一般人だけでなく、大学の哲学教授や自称哲学者にもみられるので、特に詳述しておきたい。
一般に、高校の倫理の授業や大学の一般教養課程等で、人生で初めて哲学に触れる人々は、まずはじめに「哲学の歴史」を講義されることが多いと思われる。そこにはプラトンやアリストテレス、孔子、カント、ヘーゲルといった有名な哲学者達が登場し、彼らが提唱した概念(例:プラトンならイデア、アリストテレスなら質料と形相、孔子なら仁、カントなら超越論的観念論、ヘーゲルなら弁証法etc)がざっくりと解説され、その学説を後続の哲学者がどのように批判・発展させていったかが歴史の流れに沿って紹介されていく。
ところで、多くの人々は、こうした講義を通して哲学の―正確には哲学史の―基礎的な知識を身につけ、少し哲学(史)について詳しくなると、「哲学とは、歴史上の哲学者たちの学説を学ぶことだ」という認識を持つようになる。そしてプラトンのイデア説やカントの超越論的観念論について詳しくなることが、すなわち哲学することだと思い込む。
しかし、これは哲学を学び始めた者がもっとも陥りやすく、かつ抜け出しがたい誤りである。「哲学」という営みは、「哲学史」を学ぶことと決してイコールではない。
「哲学」と「哲学史」の違いを、もっとも有名な哲学者のひとりであるカント(Immanuel Kant, 1724~1804)を例に考えてみよう。以下、少々長い哲学史の話が続くが、哲学と哲学史の違いを考えるために必要なのでお付き合いいただきたい。
イマヌエル・カント(画像はWikipediaより引用:Kant gemaelde 1 - イマヌエル・カント - Wikipedia
イマヌエル・カントが生きた18世紀の西洋哲学では、「人間はどのようにして認識を得ることができるか」という問題が多くの哲学者達によって議論されていた。大きく二つの立場が存在していた。「人間は経験によって認識を得る」と考える「経験論」(イギリス経験論とも呼ばれる)と、「人間には経験によらずに認識を得ることができる能力があらかじめ備わっている」と考える「合理論」(大陸合理論とも呼ばれる)である。若き日のカントは、合理論的な考え方を素朴に抱いていた。
しかし、彼の立場はイギリスの経験論哲学者デイヴィッド・ヒューム(David Hume,1711~1776)の哲学に直面し、根本的に揺さぶられる。
ヒュームによれば、人間は「知覚の束」にすぎない。これは、人間は生きている間、その絶え間なく繰り返される瞬間毎に受け取る知覚の背後に、なんらかの実体を確実に認識することはできない、ということである。平たくいえば、「人間が何か実体を確実に認識することなど、できやしない」という意味である。このヒュームの理論は「懐疑論」と呼ばれる。
ディヴィッド・ヒューム(画像はWikipediaより引用:David_Hume.jpg (825×1000) (wikimedia.org)
ヒュームの懐疑論はカントに大きな衝撃を与えた。とりわけカントにとって、懐疑論は宗教的に深刻な意味を持った。
幼少期からカントは敬虔なキリスト教信者である母の手で育てられていた。当然カント本人も聖書の教えを信じていた。人間は肉体が滅んでも魂は不滅であり、神を信じる者は天国に行き、信じない者は地獄に墜ちるというのがカントの信念であった。しかし、ヒュームの言うように、人間が実体を確実に認識することが出来ないとするなら、どうしてイエスが神の子であることや、神による魂の救済が真実であると断言できようか。目に見えている(と感じている)ものでさえ確実に認識することができないなら、神や魂といった不可視の存在について認識することができるはずがない。
とすれば、今までキリスト教を信じてきた自分の人生は、いったい何だったのだろうか?魂の不滅を、神の救済を信じて生きてきた自分の人生は、全て間違っていたのだろうか?
ヒュームの懐疑論によって、カントの素朴な合理論的立場は打ち砕かれた。そうかといって、懐疑論はカントにとって何としても受け入れがたい結論であった。それは自身の生き方に関わる問題であった。ここからカントは、ヒュームの懐疑論を前提としながらも、神や魂といった不可視のものを認識することがいかにして可能なのかを、死にものぐるいで模索することになる。そうして10年近くもの歳月を思考に費やし完成したのが主著『純粋理性批判』である。以下、哲学と哲学史の違いを考えるために必要な範囲内で『純粋理性批判』の内容を概説する。
カントは、一見対立する見方である経験論も合理論も、「認識とは対象をそれ自身においてある姿において把握することだ」という見方に立っている点で実は共通していることに着目した。この見方が結局はヒュームの懐疑論を導いてしまうのならば、一度「認識」というものについてはじめから考察し直すことで、ヒュームの懐疑論を再検討する必要があるとカントは考えた。そこで彼は人間が物事を認識する能力である「理性」についてまず考察することにした。
従来の哲学では、認識される対象がまず先にあって、その対象を人間が理性によって認識するのだ、と考えられていた。いわば「対象→認識」という順番で考えられていた。しかし、カントはむしろ逆で、まず人間の認識があって、その認識の形式によって対象が構成されるのだ、と考えた。いわば「認識→対象」という順番で考えたのである。これは哲学史的に見て、今までの見方を転換する画期的な事件であり、哲学の「コペルニクス的転回」と呼ばれる。カントは、ヒュームのいうように、人間は経験によって対象を認識するのだと考えたが、それと同時に人間には対象を対象たらしめる能力が経験に先立って先天的に(ア・プリオリに)備わっているとも考えた。カントはこのことを「超越論的」( transzendental)と呼んだため、カントの哲学は「超越論的観念論」ともいわれる。
さて、カント哲学が生まれた経緯とカント哲学の内容を少し長めに概説してきたが、以上の話を踏まえた上で本題の「哲学」と「哲学史」の違いに戻ろう。
カントは、「哲学史」的に見れば、認識と対象の関係に新たな視点を提示し、超越論的観念論という独自の哲学を打ち立てた哲学者だということになるであろう。しかし、そのことは本当はそれほど重要なことではない。「哲学」的に見れば、カントの哲学は一貫して宗教上の問題であった。「神や魂といった不可視の存在を認識することはいかにして可能か?」という問いは、突き詰めれば「神はいるのかいないのか?魂は本当に不死なのか?」という、カントの人生観に関わる重大な問いだったのである。認識と対象に関する難解な議論や、超越論的観念論という用語自体がカントの哲学なのではない。カントの哲学とは、神や魂というもっとも崇高な問題を生涯にわたって考え続けた「生き様」そのものなのである。それこそが、私たちがカントから学ぶべき本当に大切なことなのだ。
ここに「哲学」と「哲学史」の関係をめぐる大問題がある。カントの哲学は、カント自身の生き方から直接にじみ出てきた問題だから、カント本人にとっては、それはまさしく「哲学」の問題であった。しかし、カント自身の切実な問題意識を共有していない私たちにとっては、それは「哲学史」でしかない。言い換えれば、「カント本人」にとっては「哲学」でも、「カント本人でない私たち」にとっては「哲学史」でしかない。カント本人にとっては思考そのものでも、私たちにとっては他人の思考の残りカスにすぎない。同じことの繰り返しになるが、カント本人にとっては、カントの人生とカント哲学は一心同体であるが、私たちにとっては、自らの人生とカント哲学には何ら必然的な結びつきはない。
以上述べたことを踏まえて哲学と哲学史の違いをまとめよう。哲学とは、自らの人生から必然的に生じてきた切実な問題意識を、全身で受け止め、自らの生がその解答であるかのように生きることである。これに対して、そういう哲学的な生き方をした特定の個人の思考・実践を言語によって表し、歴史の時系列順に並べたり一定の概念枠によってグループ分け(例:経験論、合理論、ドイツ観念論、実存主義、プラグマティズムetc)したものが哲学史である。いわば哲学史は哲学の抜け殻の陳列棚とでもいうべきものである。
哲学史においては、ある個人が一生を賭けて生き抜いた問いが言語によって要領よくまとめられているが、そこからは当人の真摯さ、切実さが決定的に抜け落ちている。カント哲学を超越論的観念論だの定言命法だのといった専門用語で分かったつもりになることはたやすい。しかし、カント哲学を言葉だけで理解しようとするとき、私たちはカント自身の痛切な問題意識や実感を取りこぼしてしまう。だから、哲学史的にカント哲学の知識を得ても、それでカント哲学が「分かった」ことにはならない。カント哲学が本当の意味で「分かった」と言えるには、カント自身の問題意識を共有し、カントの苦悩を骨の髄まで味わわなければならない。(※1)いわばカントの人生を追体験しなければならない。「哲学」するとは、本来それほど重く困難な営みなのである。いうまでもなくこのことはカント以外の全ての哲学者にも当てはまる。
とはいえ、では哲学史の勉強が何の役にも立たないかというと、そうではない。哲学史の知識は、私たちが哲学するときの、考えるヒントとして役立つのである。ただし、学説を勉強することが主目的になってしまい、自分の頭で考えることをおろそかにしてしまうと、それは本末転倒である。
よく武道で「守・破・離」ということが言われる。これは、最初は師匠の教えを型どおりに守ることが大切だが、それが身についたら徐々に型に囚われずに自分の型を模索し、最後には完全に師匠の型から離れて自分の型を確立することが大切であるという教えである。哲学についても同じ事が言える。最初は誰か有名な哲学者の学説や哲学史を学ぶことから始めてよい。しかし、ある程度知識が付いてきたら、段々と自前の哲学をつくっていかなければならない。それをしないでビジネス教養のために哲学書―しかも原著じゃなくて解説書!―を読んで哲学をした「つもり」になっている人は、今すぐ認識を改めてもらいたい。
3.哲学とは「問い」を生きること
前節では、「哲学とは何か」という表題に対して、「哲学は○○ではない」という否定文の形式で消極的に考えを述べてきた。本節ではより積極的に、「哲学とは○○である」という形式で考えを述べる。しかし、ここまで読んで下さった方には、私が主張しようとしていることは自ずから察しが付くであろう。
結論的に言うと、哲学とは「問いを生きること」である。自分の人生はこの問いを解決するためにあるのだと言える程の問い、この問いを無視したら自分の人生すべてが意味を失うほどの問い、そういう問いを全身全霊で生き抜くことこそ哲学である。
例えば、先のカントの場合でいえば、「ヒュームの懐疑論を前提にした上で、神や魂といった不可視の対象を認識することがいかにして可能か?」という問いを「生きる」ことが、カントにとっての哲学であった。この問いはカントにとって、単なる頭の体操ではなく、自分の全人生を賭けて解決すべき問題であったのである。このように、人生を賭けてひとつの問いと格闘し、苦悩し、自分なりの答えを模索していくことこそ、哲学することである。(※2)
ある問いを生きるということは、レストランで食べたいメニューを選ぶような、随意の事柄ではなく、「私はこの問いを生きるのだ、この問いに殉じて死ぬのだ」と「決断」することである。そしてその他一切のことを擲つことである。その決断が幸福な人生に繋がるかは分からない。むしろ不幸な人生になる可能性の方が大きいであろう。人から理解されず、批判されたり嘲笑されるかもしれない。貧乏になるかもしれない。あげくには法に逆らうことになったり、名声を失うかもしれない。それでもその問いが自分の人間性(生の全体性)を完成させることを信じて、その問いに人生を「賭ける」ことが哲学なのである。
それは裏を返せば、他の問いを生きない、他の問いを諦めるということでもある。限りある人生においてありとあらゆる問いを生きることはできない。ある問いを生きることは自分の人生の有限性、不可能性を自覚することである(※3)。しかし、人間は自らの有限性・不可能性を自覚することで、かえって無限性、永遠性へと至ることができる。このことは私が10年の思索の果てに実感した、人生の逆説である。
4.哲学的な問いの条件
前節では、哲学とは「問いを生きること」だと述べた。しかし、問いなら何でもいいというわけではない。人生には色々な問いがあり得るが、問いには「哲学的な問い」とそうでない問いがある。
たとえば「どうしたらお金持ちになれるか」とか「どうしたら女の子にモテるか」といった問いは哲学の問いとはいえない。ではどのような問いが哲学的な問いだといえるか?思うにその条件とは①問いの固有性と②問いの普遍性の二つである。
4-1.問いの固有性
問いの固有性とは、問いが、それを問う人自身の、固有の人生からにじみ出てきた問いであることを指す。先のカントの例でいえば、敬虔なキリスト教信者であったカントがヒュームの懐疑論と出会うことで、「神や魂といった不可視の存在を認識することはいかにして可能であるか?」という問いが生まれた。この問いは、他の誰でもないカント自身の人生から、カント自身の生き方に直接関わるものとして生まれたのである。問いの生まれた経緯が、その問いを問う本人の生と不可分である時、その問いには固有性があるといえる。
4-2.問いの普遍性
問いの普遍性とは、その問いが全ての人間にとって意味のある問いでなければならないということを指す。例えば「どうしたらお金持ちになれるか」や「どうしたら女の子にモテるか」といった問いは、その問いを発した当人にとっては切実な問いであり、固有性のある問いかもしれない。しかし、それはお金持ちやモテる人間になりたいと思わない人にとっては意味を持たない問いなので、普遍性がある問いだとはいえない。
固有性だけを備えて普遍性の欠けた問いは、ただのプライベートな悩みにすぎない。一方、普遍性だけを備えて固有性の欠けた問いは、社会問題や他の学問の問題と区別が付かない。例えば「ガザ地区におけるイスラエルとハマスの紛争をどう終わらせるか」という問いは、本稿執筆時(2023年12月)の国際情勢において極めて重大かつ切迫した問いではあるが、「哲学の問い」ではない。(※4)
5.私とは何か、私はどう生きるべきか
固有性と普遍性という二つの条件は、一見すると互いに矛盾している条件に見えるであろう。しかし、私が思うに、二つの条件を満たす問いが一つだけ存在する。
それは、「私とは何か、私はどう生きるべきか」という問いである。この問いこそ、全ての哲学が解こうとしてきた問いに他ならない。
なぜか。同じ人間は二人と存在しないのであるから、「私とは何か、私はどう生きるべきか」という問いには、各人各様の答えがある。この点でこの問いは常にひとりひとりに固有の問いであるといえる。しかしそれと同時に、誰もが「私」という自己感覚を備えており、この感覚抜きにしては何事も思考することはできないわけであるから、この問いは常に人類に普遍のものである。このように、固有であると同時に普遍である「私」の存在を問う「私とは何か」という問いこそ、哲学的な問いであると言える。そして「私とは何か」を考えることは、当然「私はどう生きるべきか」という問いと切り離せないわけであるから、「私とは何か、私はどう生きるべきか」という問いが哲学的な問いなのである。
私とは何かを考えることは、「私」という生を条件付けているものについて考えることである。「存在」や「時間」「空間」といった抽象的概念への問いの意義はここにある。哲学に興味の無い人は、往々にして「そんな抽象的なことについて考えて何の意味があるのか」と問うが、これらの概念について考えることは結局「私とは何か」を考えることであり、それは「私はどう生きるべきか」を考えることに繋がるのである。先のカントも、一見すると「認識」や「理性」や「対象」といった抽象的な事柄ばかり論じているが、それら抽象的概念についての思考を通してカントは「私」の謎を追求したのである。
また、問いは文字通りの「私とは何か、私はどう生きるべきか」である必要はない。真に意味のある問いは、表面的に他の命題の形をとっていても、その奥には必ず「私とは何か」「私はどう生きるべきか」という問いが含まれている。例えばキルケゴールは「神」について、三島由紀夫は「美」について生涯問い続けた思想家だが、彼らはそれらを問うことを通して「私」の問いを考えたのである。いわば、真に哲学的な問いは、すべて「私とは何か、私はどう生きるべきか」という問いの変種なのである。
6.「生哲」の提唱
哲学とは「私とは何か、私はどう生きるべきか」という問いを生きることである。これが私の哲学に対する現時点の結論である。
最後に、今述べた見地から「哲学」という言葉を振り返り、私がこの謎めいた言葉に対して考えてきたことを述べよう。
哲学とは何かを明らかにすることは、なぜこれほどまでに困難なことだったのだろうか。私には、その難しさは「哲学」という言葉それ自体に原因があるように思われる。
哲学(史)を少しでも勉強したことがある方は、「哲学」という言葉は西洋の「フィロソフィー」 (philosophy)の訳語であることをご存じであろう。この訳語は明治時代の西周(にし・あまね, 1829~1897)という学者によって、その著『百一新論』(明治7年、1874年)にて用いられたのが最初である。
西周(画像はWikipediaより引用:Nishi Amane, supervisor of the Tokyo Normal School - 西周 (啓蒙家) - Wikipedia
フィロソフィーの訳語には当初複数あって、「希哲学」「希賢学」「窮理学」「理学」等があったが、最終的に「哲学」に落ち着いたようである。以来今日に至るまで、フィロソフィーの訳語としては「哲学」が用いられ続けてきた。
しかし私が思うに、哲学という言葉は「学」の字がくせ者である。この一字のせいで今日に至るまで哲学は理解されなかったり誤解されてきたのではないか。哲学は、物理学や心理学や社会学等々の諸学問と並記されるような意味では「学」ではない。「哲学は学ぶものではなく、するものだ」ということがしばしば言われる。しかし、これは半分当たっているが、半分間違っている。なぜなら哲学は「学ぶ」ものではなく、「する」ものでもなく、「生きる」ものだからである。このことはここまで本稿を読んでくださった方なら自然と了解されるであろう。
したがって、哲学は「学問」ではない。だからフィロソフィーの訳語として「哲学」は適当ではない。
そこで私は、従来の「哲学」という訳語に代わり、「生哲」(せいてつ)という新たな訳語を提唱する。
生哲という言葉の意味は「フィロソフィー」 (philosophy)であって、従来の「哲学」と違わない。しかし、これまで何度も繰り返し述べてきたように、哲学とは生き方の態度なのである。学問は人生の中に含まれる営みの一つに過ぎないが、哲学は生きることそのものである。だから「学」という言葉よりも「生」という言葉を用いる方が、より的確にフィロソフィーの内実を示すことができると考える。(※5)
生哲という言葉が広まり、意味が理解されることで、今よりも多くの人々が「哲学的に」生きることができるであろう。それが、青春期を哲学に捧げた私が哲学にできる、ささやかな貢献である。(終)
脚注
(※1)書店には通俗的な哲学の解説書が溢れているが、ここまで読んでいただいた方には、哲学を「解説」することのおかしさがお分かりいただけるであろう。ある哲学者の哲学は、その人の苦悩やそれを生きた態度と切り離すことができない。偉大な哲学者の哲学を「理解」するには、それこそ自分の人生を全て投じる程の思考と時間と、そして覚悟がいる。だから例えば「カントの哲学をざっくり解説!」することなど、カント本人含め誰にもできるわけがない。しかるに、このようなことを謳った哲学解説書はごまんとあるのが実態である。こんな本ばかり書いている某K教授や某O教授、某S教授を、哲学への巨大な誤解を広め続けている元凶として、私は軽蔑し、非難する。
(※2)実は問いは必ずしも言語化されている必要はないのではなかろうか。というより、必ずしも言語化できないことが多いように思われる。というのも、言語化とはある対象を解釈することであるが、解釈には先だって当然解釈の対象が存在しなければならないであろう。ところがある人の生は、それが死によって完結するまでは対象として名指すことができない。例えばある偉人の生涯は、彼が亡くなって初めてその人生が何であったかが言葉によって説明することができる。それと同じで、自分の人生の問い(テーマ)が何なのかは、死の間際、あるいは死後になって初めて言語化できることなのかもしれない。
(※3)森見登美彦の小説『四畳半神話体系』の登場人物に同趣旨の台詞がある。
(※4)もっとも、哲学の成果を応用することはできる。しかしそれは例えば国際政治学や軍事学といった別の文脈において語られるのであって、「哲学」の文脈それ自体で語られるのではない。哲学の成果が別の分野に応用されるには、いったん別の分野の文脈に移らなければならないのである。
(※5)私は以前「革生学の自我論2:人生の苦しみと「絶対無」の境地について」という記事で、生と死の二項対立の根底にある「絶対無」の境地こそ、人間精神の最高段階であるということを述べた。生哲とは問いを生きることであるわけだが、これは当然「問いに死ぬ」ことと表裏一体である。生哲において人間は絶対無の境地へ到達することができるのである。